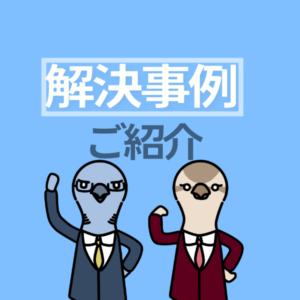遺留分侵害額請求をめぐる争いで、相続税申告期限内の早期解決を実現した事例

「故人の遺志を尊重して遺言書通りにしたいのに、他の相続人から金銭を要求されている」
「介護を一身に背負ってきたのに、長年顔も見せなかった兄弟が権利だけ主張してきて困っている」
 はと町
はと町遺産相続では、こうした根深い感情の対立がしばしば問題となります。
本記事では、遺言書で全財産を相続したものの、他の相続人から「遺留分」を請求され、相続税の申告期限内に円満な解決を実現した事例をご紹介します。
【簡単解説】遺留分(いりゅうぶん)とは?
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子など)に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を長女に」と書かれていても、長男は自身の遺留分を金銭で請求する権利があります。
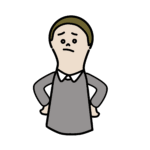
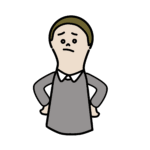
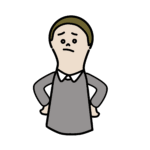
急に権利を主張されて困っています…。
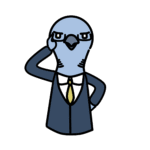
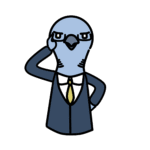
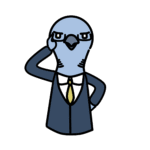
以前解決した事例の詳細をご紹介いたします。
ご相談の背景:遺言書と「遺留分」をめぐる対立
ご依頼は、お母様を亡くされた長女の方からでした。 お母様は生前、「長年にわたり闘病生活を支え、最期まで寄り添ってくれた長女に全財産を遺す」という内容の自筆証書遺言をのこされていました。遺言書には「長男には遺留分を請求しないでほしい」との想いも記されていました。
しかし、お母様の逝去後、長年交流のなかった長男側から、法律上の権利である「遺留分侵害額請求」がなされました。
ご依頼者様は、故人の想いを無下にするような長男の対応に心を痛めつつも、争いを長引かせたくないという思いから、「相続税の申告期限内に、妥当な金額で早期に解決したい」とご希望でした。
早期解決へ導いた交渉ポイント3つ
遺留分の請求は正当な権利であるため、支払いを完全に拒否することは困難です。
そこで弁護士は、単に相手の要求を飲むのではなく、ご依頼者様が納得できる「妥当な解決」を目指し、以下の3点を軸に交渉を進めました。
≪早期解決へ導いた交渉ポイント3つ≫
1.故人の想いと介護の事実を丁寧に主張
まず、交渉の前提として、ご依頼者様が長年お母様の介護に尽くされてきた事実や、お母様自身が「ささやかな家族葬」や「墓じまい」を望んでいたことなどを、書面を通じて相手方に丁寧に伝えました。これは、法的な主張とは別に、公平な解決に向けた素地を作るための重要なステップでした。
2.公平な費用負担を盛り込んだ解決案を提示
相手が請求する遺留分額から、ご依頼者様が一人で負担していた葬儀費用や墓じまい費用について、法定相続分に応じた負担を差し引くことを提案。さらに、相続税の負担についても調整を図り、双方が公平に義務を分担する形での合理的な解決案を提示しました。
3.裁判例に基づく不動産評価を主張
本件では、遺産に含まれる不動産の評価額が大きな争点となりました。相手方は簡易的な査定に基づき、高めの評価額を主張していましたが、当方は裁判実務でも用いられる「路線価」を参考に評価すべきだと反論。関連する裁判例も示しながら粘り強く交渉し、公正な評価額を基準に解決金を算出することに成功しました。
結果:申告期限内に、納得の和解成立
交渉の結果、当初相手方が請求していた金額から減額し、相続税申告の期限内に、解決金の一括払いで和解を成立させることができました。法的な争点だけでなく、ご依頼者様の感情面にも配慮しながら交渉を進めたことで、早期かつ円満な解決に至りました。
担当弁護士より
遺留分は法律で認められた権利ですが、その金額の算定や、葬儀費用などの分担については、交渉の余地が大きく残されています。相手の言い分を鵜呑みにせず、法的に適正な金額で妥当な解決を図るためには、専門的な知識と交渉力が不可欠です。
当事務所は、ご依頼者様のお気持ちと故人の想いを丁寧に汲み取り、法的な根拠に基づいて粘り強く交渉することで、ご納得いただける解決を目指します。
《依頼者様の声》 「迅速に対応していただき、希望していた通りの期間内での解決に至りました。色々と手厚くサポートして頂き、質問にも一つひとつ丁寧に答えて頂けましたので、終始安心して進めることが出来ました。お世話になりました。」
相続をめぐるトラブルは、精神的なご負担も大きい問題です。