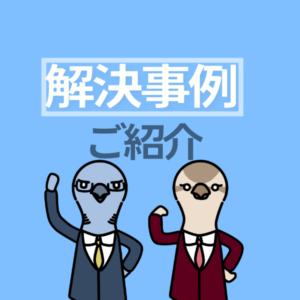【解決事例】被相続人が亡くなった場所がわからない?相続放棄の申述が受理された事件

「亡くなったことは分かったが、どこに住んでいたか、財産や借金がどうなっているか全く分からない」
このような状況に置かれ、ご不安な思いをされている方は少なくありません。
本記事では、当事務所が実際に解決した、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地が分からなくても相続放棄が認められた事例をご紹介します。
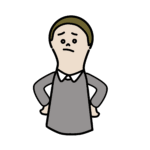 依頼者
依頼者亡くなったらしいんだけど、住所や財産についてなど、全く分からないんだ…
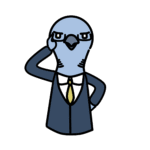
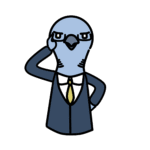
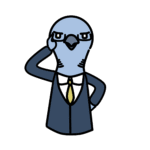
大丈夫です!
疎遠な親の相続、最後の住所が不明でも相続放棄は可能です!
以前解決した事例の詳細をご紹介いたします。
目次
ご相談の背景:疎遠な親の相続、住所が不明だが、相続放棄したい
ご相談者様のお母様(申述人)の元に、遠方の市役所から「空き家等の適切な管理に関する依頼書」という一通の書面が届いたのが始まりでした。
驚いて役所に問い合わせたところ、お母様のご実父、つまりご相談者様の祖父が亡くなっていることが判明しました。
弁護士が詳しくお話を伺うと、以下のことが分かりました。
・借金などがあった場合に責任を負いたくないため、相続放棄をしたい。
・お母様が幼い頃に両親が離婚。それ以来、ご実父とは何十年も会っておらず、完全に疎遠だった。
・どこに住み、いつ亡くなったのかも今回の通知で初めて知った。



ご相談者様のお母様よりご依頼を受け、相続放棄の申述の準備に取り掛かりました。
弁護士の対応と手続きの流れ:調査と裁判所への丁寧な説明
ご依頼を受け、弁護士は早速、ご実父の戸籍を収集する調査を開始しました。
- 戸籍調査で判明した事実
戸籍を辿っていくと、ご実父が20年以上前に亡くなっていたこと、そして最後の戸籍から、どの市区町村にお住まいだったかまでは特定できました。 - 立ちはだかった壁
しかし、亡くなってから長期間が経過していたため、役所での保管期間を過ぎており、正確な住所地を証明する「戸籍の附票」はすでに廃棄されていました。これにより、「最後の住所地」を番地まで特定することが困難な状況に陥りました。 - 裁判所への申立てと交渉
そこで弁護士は、相続放棄の申立書に、これまでの調査経緯を詳細に記載。「戸籍の附票が廃棄済みで、これ以上は調査が難しいこと」を丁寧に説明しました。 また、相続放棄の期限(熟慮期間)である「相続を知った日から3か月以内」という要件についても、「役所からの通知で初めて死亡の事実を知った日」が起算点であることを明確に主張しました。
※申立て前には、管轄の家庭裁判所に事前連絡し、法務局への死亡届の照会といった、より複雑な調査までは不要であることを確認。依頼者様のご負担を軽減しました。
<結果>
これらの主張が認められ、無事に相続放棄の申述は受理されました。
本解決事例の3つのポイント
≪本解決事例の3つのポイント≫
- 「相続放棄は死亡から3か月以内」は誤解です
相続放棄を検討する期間(熟慮期間)は、原則として「ご自身が相続人であることを知った時から3か月」です。被相続人が亡くなってから何年、何十年と経過していても、その事実を最近知ったのであれば、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。 - 最後の住所が不明でも諦めないでください
本件のように、被相続人の最後の住所や死亡日がすぐに分からなくても、戸籍を中心に可能な限りの調査を行い、その経緯を裁判所にきちんと説明することで、相続放棄が認められる道はあります。 - 「空き家の通知」は相続問題のサインかもしれません
役所や管理会社から、心当たりのない不動産に関する通知が届いた場合、それはご自身が相続人になっているというサインかもしれません。放置せず、お早めに弁護士へご相談ください。
「自分も同じような状況かもしれない」と感じられた方は、一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。



最善の解決策を一緒に見つけていきましょう!