不動産評価額を丁寧に立証し、相手方請求額1200万円超→300万円で和解へ【遺留分侵害額請求】
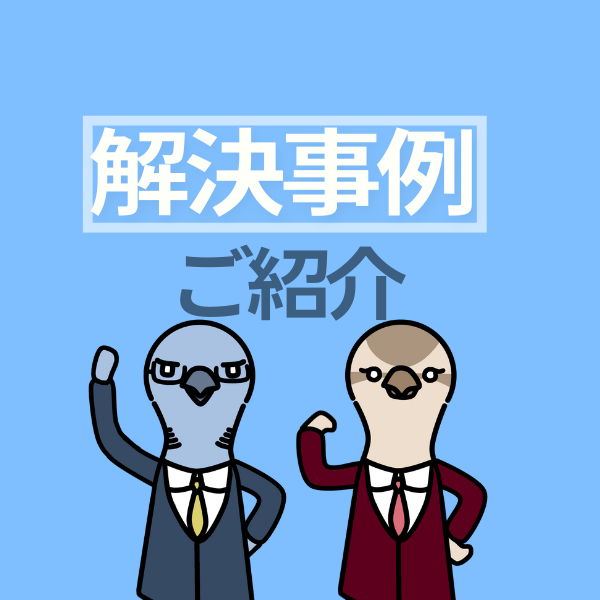
近年、相続をめぐるトラブルの中でも「遺留分侵害額請求」は増加傾向にあり、特に生前贈与や複数の遺言が存在するケースでは、法律的な争点が複雑に絡み合い、長期化・深刻化しやすい傾向があります。
本件はまさにその典型例といえるもので、依頼者が過去に被相続人から贈与を受けた不動産について、相手方から1200万円超の遺留分侵害額請求を受けたケースです。
しかし、相手方提出の不動産査定書が根拠とならない旨を主張し、さらに、そして不動産鑑定士による適正な評価を通じて交渉を尽くした結果、最終的には300万円の支払いで和解成立。
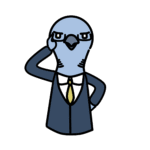 はと町
はと町弊所の解決事例のご紹介です。
ご相談の背景
本件は、被相続人の死亡に伴い、相手方(原告)から当職の依頼者(被告)に対して、遺留分侵害額請求訴訟が提起された案件です。
原告は、被告が生前に贈与を受けていた複数の不動産をすべて遺留分の基礎財産に含めるべきと主張し、1200万円を超える高額な請求を行っていました。
これに対し当方は、遺言書の有効性を丁寧に立証するとともに、不動産評価の適正性や贈与の時期・内容について法的根拠をもとに主張し、最終的には300万円の一括支払いによる和解に至りました。
弁護士による対応
以下、3つの対応を行いました。
① 不動産鑑定士による不動産評価
原告側は、不動産業者による簡易査定書に基づき、過大ともいえる評価額を主張していました。
しかし、当方では依頼者の納得のいく形での解決を図るべく、不動産鑑定士をご紹介し、適正な鑑定評価を取得。
② 自筆証書遺言の有効性を丁寧に主張
本件では、公正証書遺言と自筆証書遺言が併存していたものの、当事務所の依頼者が根拠としていたのは後に作成された有効な自筆証書遺言でした。
③ 贈与の範囲と評価に関する法的主張
相手方は、十数年続いてきた暦年贈与は被相続人の意思に反した贈与である等と主張しました。
そこで、当方は、各贈与登記時の書類や贈与証書を提出し、被相続人の意思に基づき贈与がなされてきた旨の主張、立証を行いました。そして、原告の主張する「10年以上前の贈与」については民法1044条に照らして遺留分算定の対象外であることを主張。
解決の内容
当初、原告は1200万円超の遺留分侵害額の支払を求めていましたが、最終的には当方提案の和解案(解決金300万円)をベースとした解決に至りました。
弁護士コメント
本件では、不動産評価の妥当性や遺言の有効性、贈与の範囲など、多数の法律的争点が複雑に絡んでいました。特に、不動産評価額の交渉にあたっては、不動産鑑定士の関与によって当方の正当な評価が認められたことが大きなポイントです。
また、遺留分侵害額請求は法律上認められた正当な権利ですが、これに対してどのように評価し、どの金額が法的に妥当なのかを見極めるには、高度な法律知識と実務対応力が必要不可欠です。
弊所としては、依頼者の想いや利益を最大限に尊重しつつ、冷静かつ論理的に対応することで、適正な金額での円満解決を実現することができたと考えております。

























