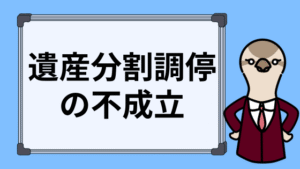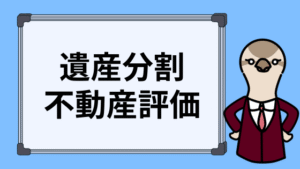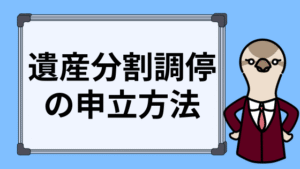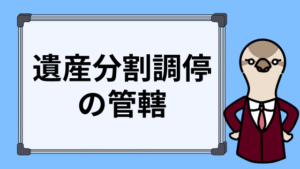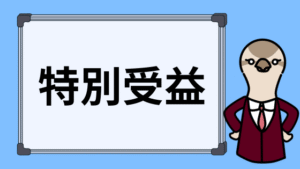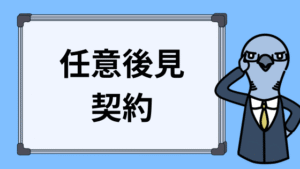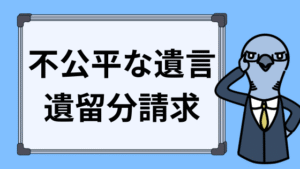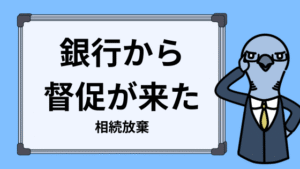任意後見と遺言の違いは?生前の備えを整理して相続をスムーズに
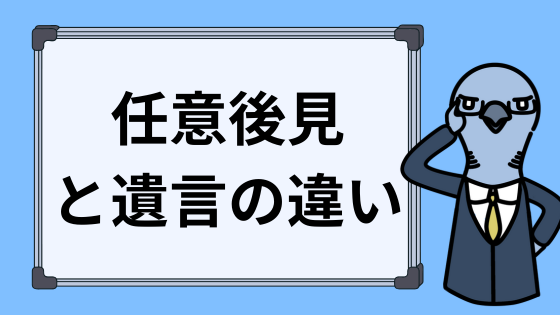
「相続人が遺産で揉めないように、元気なうちに財産の管理や相続の対策をしておきたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご本人の意思がしっかりしているうちに対策をしておけば、ご本人の意思を反映させつつ、遺産相続をスムーズに行えるような準備をしておくことが可能です。
具体的には、任意後見契約を締結しておくことや遺言書を作成しておくことが挙げられます。
本記事では、任意後見と遺言の違いや、相続対策としての活用法について解説します。
将来の遺産相続対策のため、任意後見や遺言の利用を考えている方がいらっしゃいましたら、参考にしてみてください。
元気なうちに遺産相続対策をしておく重要性
まだ元気なうちに遺産相続の対策をしておくことは重要です。
認知症などになって判断能力が低下してしまった後では、自分の意思を相続に反映させるための措置をとることはできなくなってしまいます。
また、判断能力が低下してしまうと、財産の管理などができなくなり、遺産相続が開始した場合に、相続人が調査や整理などで困る事態になってしまうこともあり得ます。
自分の意思を相続に反映させつつ、遺産相続をスムーズに行えるような準備をするためには、判断能力がしっかりしている元気なうちに対策をしておかなければならないのです。
遺産を遺す人(被相続人)が生前に行える遺産相続に向けての準備・対策として、任意後見と遺言があります。
任意後見と遺言の違い
任意後見とは、判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見人になって欲しい人の間で、代理にしてもらいたい法律行為を定めた任意後見契約を締結しておくという制度です。
他方、遺言とは、自分が亡くなって相続が開始された場合に備えて、遺産(相続財産)の相続分や分配方法などを決めておくという制度です。
任意後見と遺言は、いずれも、生前にご本人で行うことができ、また、ご本人の意思を尊重する効果を持っています。
もっとも、任意後見が生前に効果を発揮する制度であるのに対して、遺言は死後に効果を発揮する制度であるという根本的な違いがあります。
以下では、任意後見と遺言の具体的な違いについて説明します。
目的の違い
任意後見の目的は、判断能力が衰えた場合に備えて、自分の財産管理や身上監護に関する法律行為を代わりに行ってもらう任意後見人を選んでおくことです。
これに対して、遺言の目的は、自分が亡くなった場合に備えて、遺産の分配方法などを決めておくことです。
任意後見と遺言では、生前に判断能力が衰えた場合への備えと死後の備えという目的の違いがあるのです。
効力発生期間の違い
任意後見契約は、ご本人の判断能力が衰え、家庭裁判所で任意後見監督人と呼ばれる人が選任されたときから、ご本人が亡くなるまでの間に効力を発揮します。
これに対して、遺言は、ご本人が亡くなった後に効力を発揮します。
ご本人の死亡によって任意後見契約の効力がなくなり、代わりに遺言の効力が発生するという順序です。
内容面での違い
任意後見契約は、任意後見人を誰にするか、どのようなご本人の財産管理や身上監護に関する法律行為の代理権を任意後見人に認めるかなどを定めることになります。
他方、遺言は、相続人の相続分、遺産分割の方法、第三者に対する遺贈、誰を遺言執行者に指定するかなど遺産相続に関わることを定めるものです。
手続面での違い
任意後見契約は、ご本人と任意後見人となる人との間で、公正証書で作成した任意後見契約書を取り交わして締結します。
そして、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことによって、任意後見契約の効力が発生します。
他方、遺言も、自筆証書・公正証書・秘密証書という3つの方式のいずれかで書面を作成しなければいけませんが、契約ではないので、ご本人が単独で作成することができます。
また、適正な方式で作成されれば、それだけで遺言には効力があります(実際に効力が発生するのは、相続が開始してからです。)。
自筆証書遺言(法務局に保管していない場合)や秘密証書遺言の場合は、相続開始後に相続人が家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要はありますが、作成自体には、裁判手続を要しません。
遺産相続対策として任意後見と遺言を活用する方法
遺産を遺す立場として、自分の意思を反映させつつ、できる限りスムーズな遺産相続になるよう準備するために、任意後見や遺言を利用することは効果的です。
以下、その理由について説明します。
遺言書の活用
生前にできる遺産相続対策と言えば、最初に思いつくのは遺言でしょう。実際、生前の遺産相続対策の中心は、遺言の作成です。
したがって、元気なうちに第一にやっておくべき対策は、遺言書を作成することです。
ただし、やみくもに作成しても意味がありません。誰にどの財産をどの程度分配するかを計画し、それを遺言に落とし込む必要があります。
また、実際にご本人が亡くなり相続が開始された場合に、遺言の内容を実現してもらう人(遺言執行者)も、遺言で決めておくことができます。
なお、遺留分には気を付けておく必要があります。
兄弟姉妹以外の相続人(被相続人の子、直系尊属、配偶者)には、遺留分という最低限度の遺産の取得分が保障されています。
遺留分は、遺言によっても侵害できません。遺留分を侵害する遺言の部分は無効になってしまいます。
誰か特定の相続人や受遺者に対して法定相続分を超える遺産を分配する場合には、遺留分を持つ相続人がいるかどうか、いる場合にはどのように調整するのかをよく考えて遺言を作成する必要があります。
任意後見契約の活用
前記のとおり、任意後見契約は、ご本人の生前に効力を発揮する契約です。そのため、遺産相続対策にはならないように思われるかもしれません。
しかし、任意後見契約を締結して任意後見人に財産管理などを行ってもらうことにより、判断能力が低下した後でも適切な財産管理が可能になります。
適切に財産管理をしておくことは、遺産(相続財産)を確保することにもつながりますから、スムーズな遺産相続の実現に貢献します。
遺言と任意後見の併用
遺言や任意後見は、それぞれ単体でも効果的ではありますが、併用した方が、より遺産相続をスムーズにするための準備として効果が上がります。
任意後見契約をしていれば、ご本人が企図していた遺産の分配方法などの計画に沿って財産管理などを行っている途中で万が一判断能力が衰えた場合でも、任意後見人がご本人の意思に沿う形で計画を進めてくれます。
それにより、途中で頓挫することなく、ご本人の企図していた計画に基づいて財産管理などが行われ、遺産相続のときまで継続できることになります。
そして、本人が亡くなり、実際に遺産相続が開始された場合には、遺言があるため、本人の意思に基づいて遺産の分配等が行われます。
遺言と任意後見を併用すると、判断能力が低下してから亡くなった後まで、ご本人の意思を尊重する一貫した方針で、遺産相続対策をすることが可能になるのです。
任意後見人と遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を同じ人にしておくと、よりスムーズに遺産相続を進めてもらえるでしょう。
その他の方法の活用
スムーズな遺産相続を実現するために生前に準備できるものとしては、任意後見と遺言以外にも、以下のような方法があります。
- 財産管理契約:本人の財産の管理を委任する契約。任意後見契約と異なり、判断能力が低下する前でも締結できます。
- 死後事務委任契約:死後の遺産管理や整理などの事務を委任する契約。任意後見契約が終了した後に効果を発揮する契約です。
これらの契約を遺言と任意後見契約に併用することで、遺言や任意後見契約の効力が発生しない隙間を埋めることができます。
より一貫した確実な対策を行いたい場合には、上記の各契約も検討してみてもよいかもしれません。
まとめ
以上のとおり、任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるための生前に効力を発揮する制度であり、遺言は、死後に効力を発揮する制度であるという違いはあります。
しかし、これらを併用することで、ご本人の意思を反映しつつ、スムーズな遺産相続を実現するための生前対策として活用できます。
当事務所でも遺産相続に関する各種のご相談を承っています。任意後見契約や遺言の活用をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。