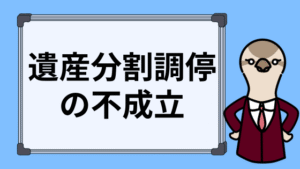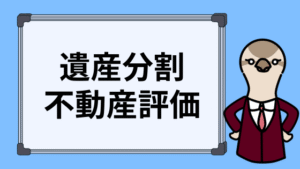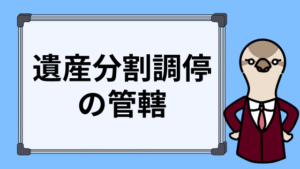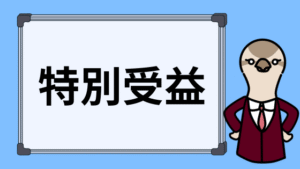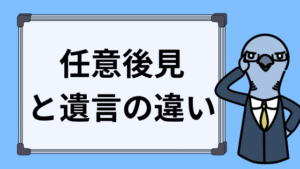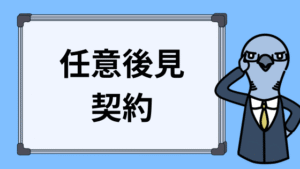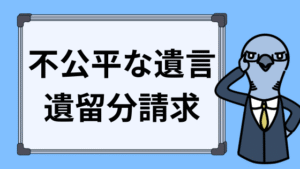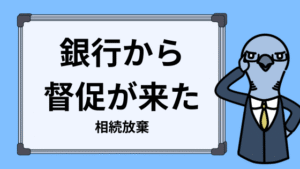遺産分割調停の申立方法を分かりやすく解説 ─ 必要書類・費用・流れをステップごとに確認
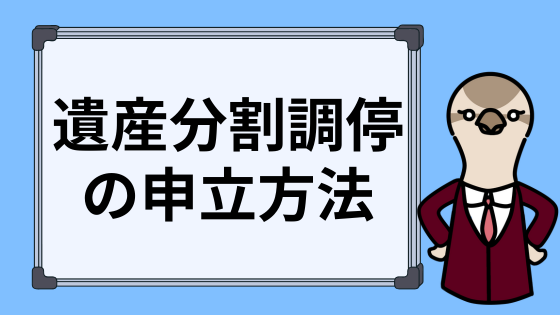
遺産の分割について相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。
しかし、実際に申立てを行うにあたっては「必要書類は何か」「費用はいくらかかるのか」「手続きの流れはどう進むのか」といった点が分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割調停の申立て方法について、必要書類・費用・手続きの流れを順番に整理しながら分かりやすく解説します。
遺産分割調停をお考えの場合は、ぜひご一読ください。
遺産分割調停とは?
相続が開始された場合、相続人が複数人いるときは、その共同相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割について話し合う必要があります。
しかし、協議を重ねても意見がまとまらない、特定の相続人が話し合いに応じないといった理由で、協議が停滞してしまうケースは少なくありません。
このような場合、次のステップとして、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります(なお、遺産分割に関しては、調停前置主義が取られていないことから、相続人間で協議が整わなかったときには、遺産分割審判の申し立てをすることも手続上は可能です)
遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官や家庭裁判所が選任した調停委員を間に入れて話し合いを行う裁判手続きです。
調停委員の構成は、実務上、男女のペア、うち1名が弁護士ということが多いです。
この遺産分割調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場から相続人の意見を整理し、合意形成をサポートしてくれます。
そのため、相続人同士の直接的な対立を避け、冷静な話し合いの場を設けることができるため、感情的な対立が激しいケースでも有効な解決手段となります。
遺産分割調停の申立ての7ステップ
前記のとおり、遺産分割協議が調わなかった場合、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
とは言え、遺産分割調停は、協議と違って裁判手続きです。法律で決められたルールに従って申立てをしなければなりません。
具体的に言うと、遺産分割調停の申立ては、以下の7つのステップで進めていきます。
ステップ1:管轄裁判所の確認
まず、遺産分割調停の申立てを行うべき家庭裁判所はどこなのかを確認します。
遺産分割調停の管轄は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。相手方が複数いる場合は、そのうちのいずれか1人の住所地を管轄する家庭裁判所を選ぶことができます。
なお、共同相続人全員が合意した家庭裁判所に申し立てることも可能です。この場合には、共同相続人が合意していることを明らかにするため、管轄合意書を作成しておく必要があります。
ステップ2:必要書類の収集
遺産分割調停の申立てには、多数の書類が必要です。
戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書など、市町村役場や法務局で取得しなければならない書類も多いため、計画的に準備を進めることが重要です(詳細は後述します。)。
ステップ3:申立書の作成
遺産分割調停の申立ては、遺産分割調停の申立書という書面を作成し、これを管轄の家庭裁判所に提出する方式によって行う必要があります。
遺産分割調停の申立書の書式やひな形は、家庭裁判所に行けばもらえます。また、インターネットで、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
入手した申立書の書式に従って、必要事項を記載して作成します。この申立書には、申立人・相手方の情報、被相続人の情報、申立ての趣旨と理由、遺産の内容などを詳細に記載します。
ステップ4:添付書類の準備
遺産分割調停の申立ては、ただ遺産分割調停の申立書を提出すれば足りるものではありません。各種の書類を申立書に添付して提出する必要があります。
ステップ2で収集した必要書類を申立書に添付して、申立ての準備を完成させます。必要書類の不足がないか、期限が切れていないか、念入りに確認しましょう。
ステップ5:費用の支払い
遺産分割調停の申立てをする際は、裁判所に手数料を納付する必要があります。手数料は、収入印紙で納付します(費用の詳細は後述します。)。
また、郵券(郵便切手)も納付しなければいけません。この郵便切手は、裁判所からの連絡用として使用されます。
ステップ6:申立ての提出
作成した遺産分割調停申立書と添付書類、そして費用を、管轄の家庭裁判所に提出します。郵送でも提出可能です。
ステップ7:第1回調停期日の通知
申立てが受理され、申立書・添付書類に不備がないと確認されると、裁判所から申立人・相手方双方に、第1回調停期日を通知する書類と呼出状が届きます。
なお、不備があった場合には、裁判所から補正を求められます。また、追加の書類の提出が求められることもあります。
これで申立て手続きは完了です。
遺産分割調停申立ての必要書類
遺産分割調停の申立てに必要な書類は多岐にわたります。事前にしっかりと確認し、漏れがないように準備しましょう。
具体的に言うと、一般的には、以下の書類が必要となります。なお、必要書類は各家庭裁判所によって微妙に異なるため、最終的には、申立先の家庭裁判所のHPで確認するようにしてください。
遺産分割調停の申立書
前記のとおり、遺産分割調停の申立てにおいては、申立書を提出する必要があります。家庭裁判所に行けば書式をもらえます。また、裁判所のウェブサイトからダウンロードできるものもあります。
各家庭裁判所によって書式が異なることがあるので、申立てをする家庭裁判所の様式に従ったもので作成した方がよいでしょう。
当事者目録
遺産分割調停の申立書には、当事者目録を添付します。当事者目録とは、申立人および相手方の氏名・住所・生年月日・年齢・被相続人との続柄などを記載し、一覧にしたものです。
なお、裁判所によっては、当事者目録のほかに、被相続人を中心とした家系図の形で相続関係を記載した相続財産関係図の提出が求められることもあります。
相続財産目録
遺産分割調停の申立書には、相続財産目録の添付も必要です。相続財産目録とは、遺産(相続財産)を一覧にしたものです。
相続財産の種類ごとに、土地目録、建物目録、預貯金目録などに分けて作成する場合もあります。
事情説明書
遺産分割調停の申立書には、事情説明書などの添付が必要となることもあります。これは、遺言の有無、遺産分割協議の状況、遺産の一部分割の有無、被相続人の情報などの事情を記載するものです。
相続関係を証明する戸籍関係書類
相続関係を証明するための証拠として、被相続人(亡くなった人)や相続人の戸籍関係書類を提出する必要があります。具体的には、以下のものが必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式:被相続人の本籍地の市町村役場で取得します。除籍謄本、改製原戸本も含まれます。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附表:被相続人の最後の住所地を確認するために必要となります。
- 相続人全員の戸籍謄本:基本的には現在の戸籍謄本ですが、それだけでは相続人であると判明しない場合には、相続人であると分かる改製原戸籍が必要となることもあります。
- 相続人全員の住民票または戸籍の附表:申立人および相手方の住所確認のために必要とされます。
代襲相続が発生している場合には、すでに亡くなっている相続人となるはずだった人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となることもあります。
なお、法務局で法定相続情報一覧図を作成している場合には、それを提出すれば、ほとんどの戸籍を提出しなくてもよくなるため、かなり手間を省略することができます。
その他の書類・資料
上記の書類のほか、申立てに必須ではないものの、相続財産に関する書類や資料の提出が求められることがあります。
むしろ、これら相続財産に関する書類・資料は、裁判所から求められる前に、申立書とともに申立ての段階で提出しておいた方が、調停がスムーズに進められます。
例えば、以下のような書類が挙げられます。
- 遺言書
- 不動産がある場合:不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 自動車がある場合:自動車検査証、査定書
- 預貯金がある場合:残高証明書、通帳のコピー
- 株式や投資信託がある場合:残高証明書
なお、これらの書類や資料は、できる限り最新のものを用意すべきです。最低でも、申立てから3か月以内のものがよいでしょう。
遺産分割調停の申立てにかかる費用
前記のとおり、遺産分割調停も裁判手続ですから、裁判手数料がかかります。また、連絡用の郵券(郵便切手)の予納も必要です。
申立て手数料(収入印紙代)
申立手数料として被相続人1人につき1200円が必要です。手数料は、収入印紙で支払います。1200円分の収入印紙を申立書に貼付して提出します。この際、割り印をしてはいけません(割り印は裁判所が行います。)。
予納郵券(郵便切手)
裁判所からの連絡・書類送付用の郵便切手です。手数料と違い、予納郵券の種類や金額は裁判所によって異なり、また、当事者の人数によって変わります。
大阪家庭裁判所では、当事者の人数が2名(申立人1名、相手方1名)の場合は、5000円、当事者の人数が3名(申立人1名、相手方2名)の場合は、7500円とされています。切手の内訳も指定されていますので、必ず申立先の家庭裁判所で確認するようにしましょう。
その他の費用
申立てそのものにかかる費用ではありませんが、戸籍謄本や住民票の取得費用、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得費用、郵送代、交通費などが別途かかります。
まとめ
遺産分割調停は、相続人間の話し合いを円滑に進め、公平な遺産分割を目指すための有効な手段です。
申立てには多くの書類が必要となり、手続きも複雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつのステップを丁寧に踏むことで、おひとりでも申立は可能だと思います。
もっとも、当事者間の協議が整わず、遺産分割調停の申立の段階に至っている場合には、調停において納得のいく解決に近づけるように、弁護士に依頼することも検討されても良いかと思います。
Leapal法律事務所では、遺言相続問題に注力しており、遺言相続の相談に関しては、初回相談無料で実施しております。是非、お気軽にご相談ください。