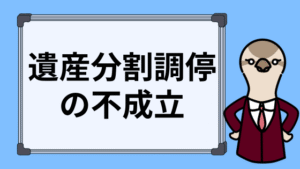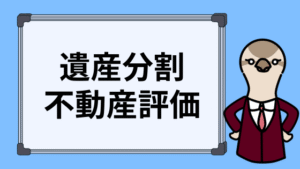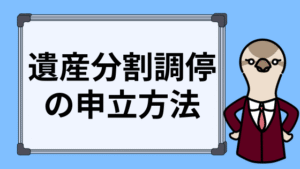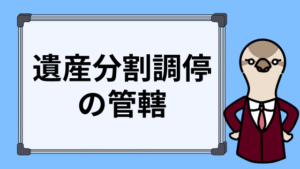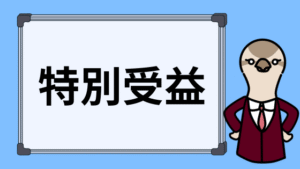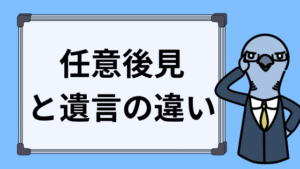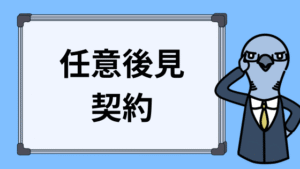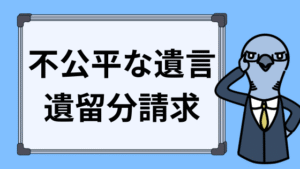【弁護士解説】金融機関から「相続人だから払え」と督促状が届いた!相続放棄の手続きと注意点
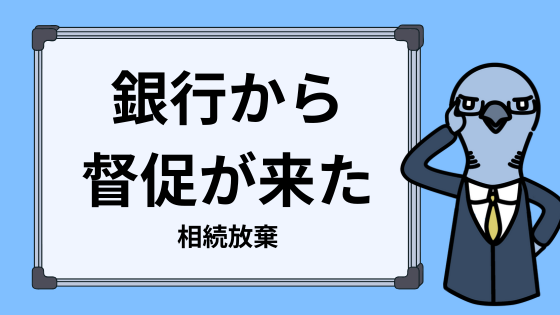
「突然金融機関から督促状が届いた」「知らない借金の請求書が郵送されてきた」――このようなお悩みの方はいませんか?
遠い親戚が亡くなった後、しばらく経ってから金融機関から相続債務の督促状が届くケースのご相談をよく受けております。
こうした状況に直面すると、多くの方が「もう手遅れなのではないか」「3か月以上経っているから相続放棄はできないのでは」と不安を感じられることでしょう。しかし、実際には適切な手続きを行えば、相続放棄が可能な場合があります。
本記事では、金融機関からの督促を受けた場合の相続放棄の方法と重要な注意点について、詳しく解説いたします。
相続放棄の現状と増加する必要性
相続放棄件数の増加傾向
相続放棄に関するご相談は年々増加しており、もはや一般の方にとっても身近な法律問題となっています。大阪家庭裁判所の統計データによると、相続放棄の申立件数は以下のような右肩上がりの推移を示しています
- 平成30年:17,466件
- 令和元年:18,101件
- 令和2年:18,905件
- 令和3年:20,691件
- 令和4年:22,682件
わずか5年間で約5000件以上の増加が見られ、相続放棄の件数が増えているいることが明確に分かります。
なぜ相続放棄が必要なのか
相続放棄が必要となる主なケースは以下の通りです
- 被相続人が多額の借金を残していた場合
- 連帯保証債務が存在する場合
- 疎遠だった親族の相続に関わりたくない場合
- 相続財産よりも債務の方が明らかに多い場合
相続放棄の期間に関する基本原則と例外
民法の原則:3か月以内の期限
相続放棄には厳格な期限が設けられています。民法915条により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
判例による期限の修正
しかし、金融機関からの督促によって初めて相続債務を知った場合には、最高裁昭和59年4月27日判決が重要な指針となります。
この判決では、以下のような場合には相続放棄の起算点が修正されると判断されています
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
つまり、3か月以上前に遠い親戚が亡くなった場合であっても、金融機関からの督促状によって初めて相続債務の存在を知ったのであれば、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
金融機関の督促手続きの流れ
債務者が死亡した場合、銀行などの金融機関は通常以下のような手順で対応を進めます
- 相続人調査の実施
- 判明した相続人への通知書送付
- 通知書到達3か月後の相続放棄照会
- 相続放棄をしていない相続人の確定と回収手続き
- 全員が相続放棄をしていた場合の次順位相続人への通知
金融機関も相続人が必ずしも被相続人の借り入れを知らないことを理解しているため、いきなり訴訟を提起するような強硬な措置は基本的に取りません。まずは相続債務の存在を知らせ、相続放棄の機会を与えるのが一般的です。
そのため、督促状が届いたからといって過度に心配する必要はありません。これは金融機関が相続人を特定するための通常の手続きの一環です。
相続放棄の具体的な手続き
必要な手続きの流れ
相続放棄は単に「相続しない」と意思表示するだけでは不十分で、家庭裁判所に対する正式な手続きが必要です。
1. 相続放棄申述書と必要書類の準備
以下の書類を準備する必要があります
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の様式)
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所が求める資料
戸籍の取得範囲は申述人と被相続人の関係により異なるため、提出先の家庭裁判所に事前に確認してください。
2. 管轄家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、法定期限内に相続放棄申述書を提出します。
注意点として、提出先はどこでもよいわけではなく、必ず「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」である必要があります。
3. 相続放棄申述受理証明書の取得
無事に相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これとは別に、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得することが可能です。
この証明書は債権者への証明や他の相続人との手続きで非常に有用なため、実務上は取得しておくことをおすすめします。
相続放棄の重要な注意点
1. 期限厳守の重要性
相続放棄には厳格な期限があります。「まだ時間がある」と思っているうちに、戸籍の取得や申述書の作成に時間を要して間に合わなかったというケースは少なくありません。とにかく早めに行動することが何よりも重要です。
2. 単純承認を避ける行動
相続放棄を検討している段階で、相続財産の一部を処分してしまった場合、民法921条により「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。
法定単純承認となる恐れのある行為の例:
- 被相続人の通帳から預金を引き出す行為
- 形見分けとして財産を持ち帰る行為
- 相続財産の売却や処分
放棄を決めるまでは財産に手をつけないことが鉄則です。やむを得ない事情がある場合には、事前に弁護士などの専門家に相談することが重要です。
3. 必要書類の迅速な収集
戸籍の取得には日数を要する場合があるため、早めに準備を開始することが大切です。特に遠方の市区町村から戸籍を取得する場合は、郵送でのやり取りに時間がかかることを考慮する必要があります。
4. 複雑な事案での専門家への相談
被相続人の死亡から3か月以上経過している事案など、対応が複雑な場合は弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士であれば代理人として家庭裁判所への折衝や書類の作成・提出も可能です。
5. 次順位相続人への連絡
相続放棄をすると、自動的に次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、被相続人に子がいない場合、両親や兄弟姉妹が次の相続人になり得ます。
相続放棄が完了したことを次順位の相続人に連絡しておくことで、金融機関等から督促が届いた際の混乱を防ぎ、トラブル回避にもつながります。連絡は法的義務ではありませんが、円滑な相続手続きのための配慮として検討すべきでしょう。
よくある質問とその回答
Q: 相続発生から3か月以上経過後に債務を知った場合でも相続放棄はできますか?
A: 一定の条件を満たせば可能です。相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じることに相当な理由がある場合には、債務の存在を知った時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。
Q: 金融機関からの督促状を無視するとどうなりますか?
A: 督促状を無視すると、最終的には訴訟を提起される可能性があります。督促状が届いたら、まずは相続放棄の検討を含めて適切な対応を取ることが重要です。
Q: 相続放棄の費用はどの程度かかりますか?
A: 家庭裁判所への申立て自体は収入印紙800円程度と予納郵券で済みますが、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要になります。複雑な事案では専門家への相談をおすすめします。
まとめ
金融機関からの督促状を受け取った場合でも、適切な手続きを行えば相続放棄が可能なケースは多くあります。重要なのは以下の点です:
- 迅速な行動: 督促状を受け取ったら早急に対応を検討する
- 専門家への相談: 複雑な事案では弁護士に相談する
- 適切な手続き: 家庭裁判所への正式な申述手続きを行う
- 証拠書類の保全: 督促状や関連書類は大切に保管する
- 次順位相続人への配慮: 必要に応じて関係者への連絡を行う
相続放棄は一度しかできない重要な判断です。「手遅れかもしれない」と諦める前に、まずは専門家に相談することをおすすめします。適切な判断と迅速な行動により、多くの場合で問題を解決することが可能です。