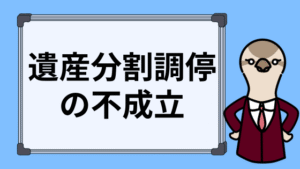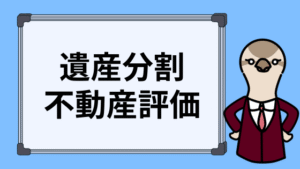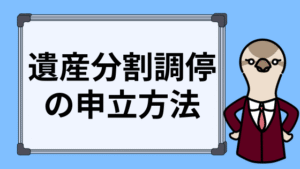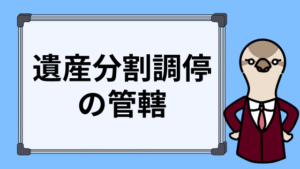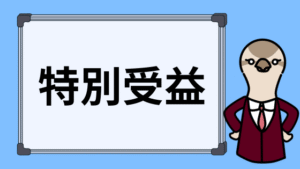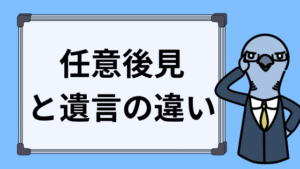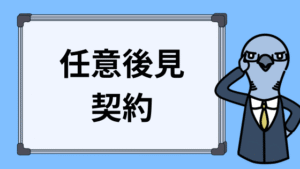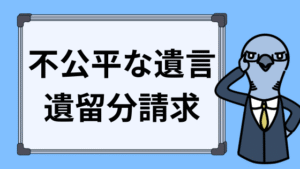【弁護士解説】配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い
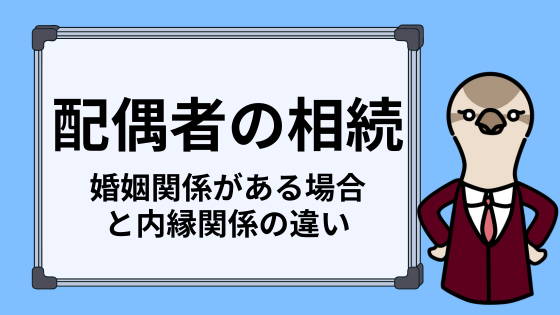
遺産相続においては、誰が相続人(法定相続人)になるのかは、民法で決められています。
亡くなった人の配偶者が相続人となるのかは、婚姻関係があるのか内縁関係にとどまるのかによって、異なってきます。
本記事では、配偶者は相続人となるのか、婚姻関係がある場合と内縁関係の場合とで違いがあるのかについて解説します。
■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■
・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~
・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント
・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い
・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い
・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは
相続人(法定相続人)となるのは誰か?
遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。
被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。
「配偶者」が相続人になるのはどのような場合?
「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」には、相続人になる順位が決められています。
第1順位は「子」、第2順位が「直系尊属」、第3順位が「兄弟姉妹」です。
したがって、子がいる場合には、子が相続人になり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
子がおらず、直系尊属がいる場合には、直系尊属が相続人になり、兄弟姉妹は相続人になりません。
子も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
これに対して、「配偶者」は常に相続人になります。他に相続人がいる場合でも、その相続人と同順位で相続人になります(民法890条)。
したがって、被相続人に子がいようと、直系尊属がいようと、兄弟姉妹がいようと、配偶者は常に相続人になれるのです。
「配偶者は常に相続人になる」の意味
前記のとおり、配偶者は、常に相続人になります。
この「常に相続人になる」ことの意味について、具体的な4つのケースをもとに説明します。
配偶者だけしかいない場合
被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もおらず、配偶者しかいない場合は、当然、配偶者が相続人になります。
配偶者と子がいる場合
被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人になります。直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
配偶者と子の遺産の分配の割合(この割合のことを「相続分」と言います。)は、遺言があれば遺言で決められた割合になります。
遺言がない場合は、民法で決められた割合になります。これを「法定相続分」と言います。
配偶者と子の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
なお、子が複数人いる場合でも、配偶者の相続分は2分の1のままです。残りの2分の1を複数人の子が頭割りで分配することになります。
子がおらず、配偶者と直系尊属がいる場合
被相続人に子がおらず、配偶者と直系尊属がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。兄弟姉妹は相続人になりません。
配偶者と直系尊属の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
なお、直系尊属が複数人いる場合でも、配偶者の相続分は3分の2のままです。残りの3分の1を複数人の直系尊属が頭割りで分配することになります。
子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
被相続人に子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
なお、兄弟姉妹が複数人いる場合でも、配偶者の相続分は4分の3のままです。残りの4分の1を複数人の兄弟姉妹が頭割りで分配することになります。
婚姻関係と内縁関係で配偶者の相続権に違いはある?
前記のとおり、配偶者は常に相続人になります。
もっとも、この常に相続人になれる「配偶者」とは、被相続人との間に婚姻関係がある配偶者を指します。
「婚姻関係がある」とは、婚姻届を提出して法律上の夫婦となっている場合のことです。
これに対して、夫婦としての実態はあるものの、婚姻届を提出していない、いわゆる事実婚の状態のことを内縁関係と言います。
この婚姻関係がない内縁関係の配偶者は、相続人になれません。相続によって遺産を受け継ぐことはできないのです。
このように、遺産相続の場面では、婚姻関係がある配偶者と内縁関係の配偶者とでは、決定的な差があります。
内縁関係の者に遺産が受け継がれるケース
内縁関係の者には、相続権はありません。したがって、相続によって遺産を受け継ぐこともありません。
もっとも、相続以外の方法で、内縁関係の配偶者が遺産を受け継ぐことはあり得ます。
遺言による遺贈がある場合
遺言で、内縁関係の配偶者に遺産を分け与えることを取り決めておくことが可能です。これを「遺贈」と言います。
遺言は被相続人の意思に基づくものですから、相続人でない内縁関係の配偶者に対して遺産を分け与えることも可能なのです。
遺贈の場合、特定の遺産だけ分け与えることもできますし、特定の財産を決めておかずに、包括的に遺産のうちの何割かを分け与えるというように決めておくこともできます。
ただし、相続人には、遺言によっても侵害できない遺留分が認められています。
したがって、遺贈によって遺留分を侵害する場合には、遺贈を受けた内縁関係の配偶者は、遺留分を侵害した相続人に対して、侵害した分の金銭を支払う必要があります。
遺産を贈与する場合
遺贈ではなく、単純に贈与の形で遺産を分け与えるケースもあります。
被相続人の生前に贈与する場合(生前贈与)だけなく、被相続人が亡くなった時に遺産を分け与える効力が発生する贈与(死因贈与)もあります。
ただし、この死因贈与の場合も、遺留分を侵害することはできません。したがって、遺贈の場合と同様、死因贈与を受けた内縁関係の配偶者は、遺留分を侵害した相続人に対して侵害した分の金銭を支払う必要があります。
相続人がいない場合:特別縁故者に該当するケース
被相続人に誰も相続人がいない場合、内縁関係の配偶者が、特別縁故者として遺産を分け与えられるケースもあります。
相続人がいない場合、その遺産は国庫に帰属することになるのが原則です。
しかし、家庭裁判所は、相続人が誰もいない場合に、被相続人と家計を同一にしていた者など特別に縁故のあった者(特別縁故者)からの請求があったときには、その特別縁故者に対して遺産の全部または一部を分け与えることができるとされています(民法958条の3)。
したがって、内縁関係の配偶者が、この特別縁故者に該当する場合には、遺産の全部または一部が分け与えられることがあるのです。
内縁関係の配偶者の居住権
被相続人が建物の賃借権を有していた場合、その賃借権は相続によって相続人に受け継がれます。
内縁関係の配偶者が、その建物に被相続人と一緒に居住していたとしても、内縁関係の配偶者には賃借権は受け継がれないのが原則です。
もっとも、相続人がいない場合には、建物の賃借権は内縁関係の配偶者に受け継がれることがあります(借地借家法36条1項本文)。
なお、相続人がいる場合、賃借権は相続人に受け継がれるので、その相続人から建物の明渡しを求められたときには、内縁関係の配偶者は建物から出ていかなければならないのが原則です。
しかし、一定の場合には、内縁関係の配偶者は、相続人からの建物明渡請求を拒絶できるとする裁判例もあります。
被相続人と内縁関係の配偶者との間の子の相続権
内縁関係の配偶者自身のことではありませんが、被相続人と内縁関係の配偶者との間に生まれた子がいる場合、その子が被相続人から認知されているときは、子として相続人なります。
また、被相続人と血縁関係はない内縁関係の配偶者の連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をしている場合は、子として相続人となります。
まとめ
以上のとおり、婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。これに対し、内縁関係の配偶者は、相続人になれません。
ただし、内縁関係の配偶者であっても、遺贈や死因贈与、または特別縁故者制度などによって、遺産を分け与えられることはあります。