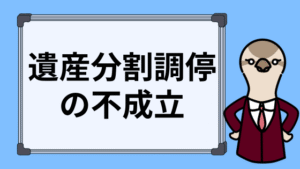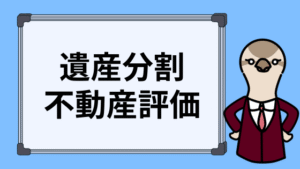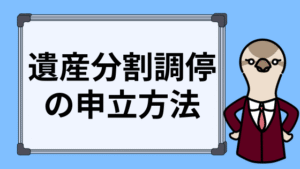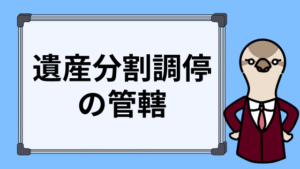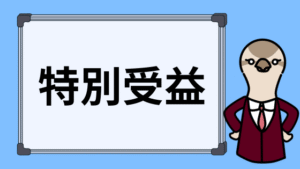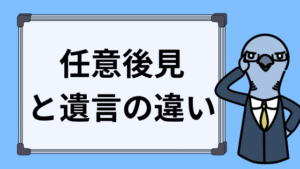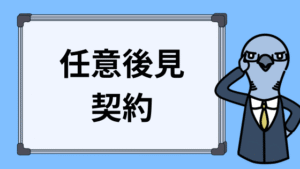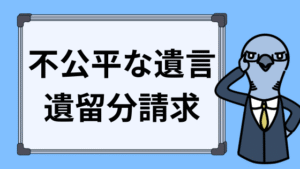【弁護士解説】長男の嫁が「介護の貢献分(寄与分)を主張してきた」法的に認められるケースとは?
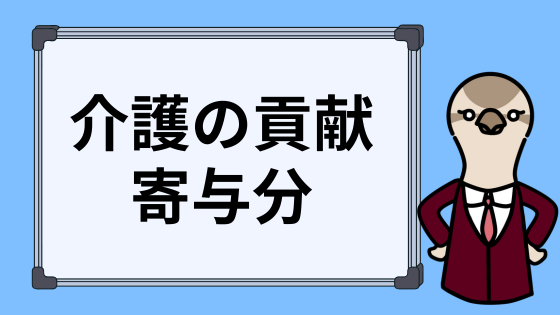
遺産相続について相続人間でトラブルになる原因の1つに、「寄与分」の問題があります。
例えば、被相続人を介護してきた相続人が、遺産の配分について介護に貢献した分を寄与分として上乗せするよう要求してくるような場合です。
本記事では、この寄与分とは何か、寄与分が法的に認められるのはどのようなケースなのかについて解説します。
相続人間で寄与分についてトラブルになって困っている方などがいらっしゃいましたら、ご一読ください。
寄与分とは?
相続人が複数人いる場合、各相続人が遺産(相続財産)を受け継ぐ割合のことを「相続分」と言います。
相続分は、遺言で指定することもできます。遺言で指定されていない場合には、民法で定められた基本的な相続分によって決まります。この民法で定められた相続分のことを「法定相続分」と言います。
もっとも、相続人の中には、亡くなった人(被相続人)の事業や生活に協力して、その財産を増やすことまたは減少するのを防ぐことに貢献した人もいます。
被相続人の財産が増えた、または、減少を防いだということは、相続人が受け継ぐことのできる遺産が増えるということです。
被相続人の財産増加などに貢献した相続人がいたからこそ、他の相続人も多くの遺産を受け取れるという恩恵に預かることができるのです。
それにもかかわらず、財産増加などに貢献した相続人もそうでない相続人も、一律に決められた法定相続分しか受け取れないというのは、公平に反します。
そこで、被相続人の財産増加に貢献した相続人の相続分を他の相続人よりも優遇しようという制度が「寄与分」です。
すなわち、寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人の相続分に、一定の寄与分を加算するという制度です。
寄与分が認められるための要件
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
ただ単に被相続人の事業を手伝っていたり、介護をしていたりしただけでは、寄与分は認められません。
寄与分が認められるためには、民法で定められた要件を満たしていなければなりません。
寄与分が認められるための要件は、以下のとおりです。
- 相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法で寄与行為をしたこと
- 寄与行為が特別の寄与であること
- 被相続人の財産が維持され、または、増加したこと
- 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加の間に因果関係があること
寄与行為
寄与分が認められるためには、相続人が、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法で寄与行為」をしたことが必要です。
寄与行為としては、例えば、以下のケースがあります。
- 家業従事型:被相続人が事業を行っていた場合に、その事業を手伝っていた場合
- 金銭等出資型:被相続人に対して、生活費や事業資金などの金銭的な援助をしていた場合
- 療養看護型:被相続人が病気になったときに、療養看護を行った場合
- 扶養型:被相続人を継続的に扶養していた場合
- 財産管理型:被相続人の財産を管理していた場合
特別の寄与
寄与分が認められるためには、寄与行為があるだけでは足りません。その寄与行為が「特別の寄与」と認められる場合でなければなりません。
被相続人と相続人は、夫婦であったり、親子であったり、または、兄弟姉妹です。
これら夫婦、親子、兄弟姉妹には、そもそもお互いに協力する義務や扶養する義務があります。つまり、お互いに助け合い、お互いに寄与行為をすることは、ある程度当然であるということです。
したがって、単に寄与行為があっただけでは当然のことをしたにすぎないため、当然とは言えない程度の「特別の寄与」をした場合に限り、寄与分という特別な利益が認められるものとされているのです。
例えば、被相続人の事業を手伝っていた場合でも、ちゃんとそれなりの給料をもらっていたような場合には、正当な対価を得ているので「特別の寄与」があったとは言えず、寄与分は認められません。
また、長年、被相続人を扶養していたとしても、扶養義務の範囲内にとどまると判断された場合には、「特別の寄与」があったとは言えず、寄与分は認められません。
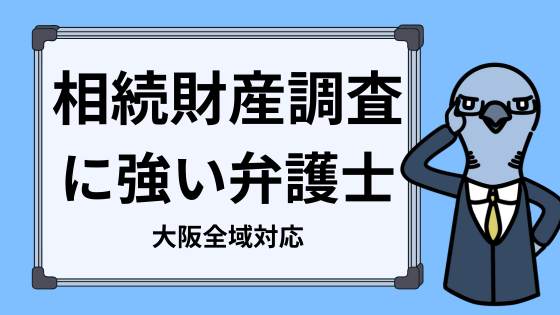
被相続人の財産の維持または増加
特別の寄与に該当する寄与行為をしていたとしても、被相続人の財産が維持され、または、増加していなければ、寄与分は認められません。
寄与分は、あくまで、被相続人の財産が維持または増加された場合にのみ認められるのです。
寄与行為と被相続人の財産の維持または増加の間の因果関係
寄与行為があり、被相続人の財産が維持または増加された結果があっても、その間に因果関係がなければ、寄与分は認められません。
因果関係があるとは、寄与行為をしたことによって、被相続人の財産が維持または増加されたという関係がなければならないということです。
したがって、寄与行為があったとしても、寄与行為とはまったく別の原因で被相続人の財産が維持または増加していたのであれば、因果関係がなく、寄与分は認められません。
介護の貢献分は寄与分として認められるか?
寄与分が争われるケースとしてよくある事例が、表題にもあるような、被相続人の介護をしていたケースです。
実際、介護は大変な労力が必要となります。介護をしていた相続人としては、介護をしていない相続人に対して寄与分を主張したくなる気持ちは分かります。
しかし、介護の貢献分が寄与分として認められるためには、前記の要件を満たしていなければならず、簡単に認められるものではありません。
特別の寄与があると言えるか?
被相続人の療養看護も寄与行為に含まれます。もっとも、「特別の寄与」と言える場合でなければ、寄与分は認められません。
被相続人を介護することは、基本的に、夫婦または親族間での協力義務や扶養義務に含まれる行為です。
したがって、特別の寄与があると言うためには、その協力義務や扶養義務の範囲を超える程度の介護をしていた場合でなければなりません。
どの程度の介護をしていれば協力義務は扶養義務の範囲を超える介護と言えるのかは、ケースによって異なります。
一般的には、無償であったか否か、継続的な介護であったか否か、専従的な介護であったか否かが、特別の寄与と言えるかどうかの判断の重要な要素とされています。
そして、被相続人の介護のレベル(要介護度)、介護の内容や介護に費やした時間などを総合的に考慮して、無償性、継続性および専従性を検討し、特別の寄与と言えるかどうかを判断することになります。
被相続人の財産の維持または増加があると言えるか?
介護が特別の寄与に当たる場合でも、それによって被相続人の財産の維持または増加がなければ、寄与分は認められません。
例えば、介護に必要となる器具や装具の購入費用、医療や介護サービスを受けるための費用などを相続人が支払っていたのであれば、被相続人の出費が抑えられ、財産が維持されたと言えるでしょう。
また、費用を支出していない場合でも、相続人が介護をしたことによって、医療費や介護サービスを受けなくてもよくなったと認められる場合には、その分の支出が抑えられたと言えるので、財産の維持があったと言えることになります。
寄与分の金額
寄与分が認められる場合、その具体的な金額がどの程度になるのかは、介護報酬の日当相当額に介護日数を乗じた金額を基準として決められるのが一般的です。
裁判例には、介護報酬額を、訪問介護など介護サービスの介護報酬基準に基づいて算出しているものがあります。
まとめ
以上のとおり、介護に貢献した場合、寄与分が認められるケースはあります。ただし、単に介護をしていたというだけで認められるほど、簡単ではありません。
寄与分を主張したい、または、寄与分を主張されているという場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。