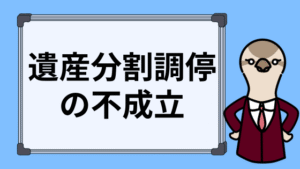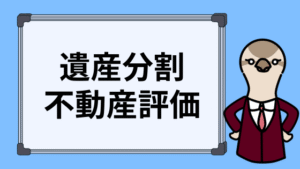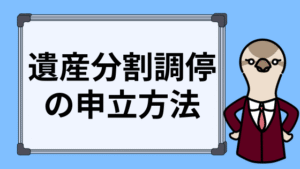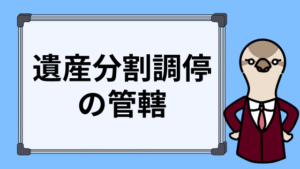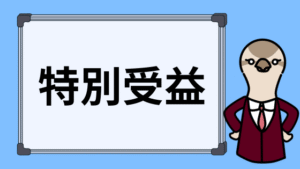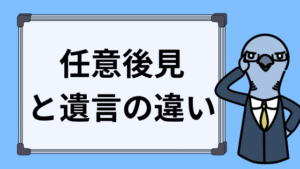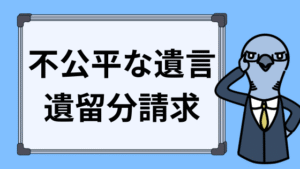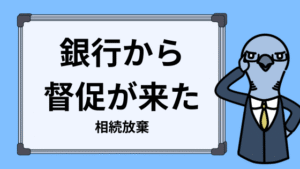親が認知症になる前にできること〜任意後見契約の実務と注意点〜
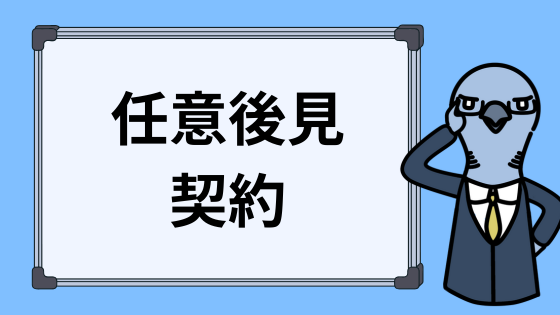
親が認知症になり、判断能力が衰えてしまった場合、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらわなければいけません。
しかし、必ずしも親の希望した人を成年後見人に選任してもらえるとは限りません。
それでは、希望した人を後見人にしてもらう方法はないのかというと、そのようなことはありません。
親が認知症になって判断能力が衰えてしまう前に、親と後見人になって欲しい人との間で任意後見契約を締結しておけば、希望した人に後見人になってもらうことができます。
本記事では、任意後見契約の実務と注意点について解説します。
親が認知症になる前に任意後見契約を締結することをお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読ください。
成年後見制度:法定後見と任意後見
親が認知症になって判断能力が衰えてしまうと、一人で財産の管理などの法律行為を行うことが難しくなってきます。
また、判断能力の低下につけこまれて不当な契約を締結させられるなどの不利益を被るおそれもあります。
そこで、判断能力が衰えた人を保護しサポートするための法制度として、成年後見制度が設けられています。
成年後見制度とは、後見人を選任して、その後見人が判断能力の衰えた人の代わりに財産管理などの法律行為を行うことができるという制度です。
この成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見とは
法定後見とは、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が、判断能力が衰えた人(成年被後見人)に代わって法律行為を行う制度です。
法定後見は、すでに判断能力が衰えてしまっている人がいる場合に、その本人や家族・親族が家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをする必要があります
この法定後見の場合、成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
申立てをする際に、成年後見人に就任してほしい人の希望を提出することはできますが、必ずしも希望どおりになるわけではありません。
特に、成年被後見人に多くの財産がある場合、家庭裁判所は、親族や知人などではなく、中立的な第三者(家庭裁判所が選んだ弁護士などの専門家)を成年後見人に選任するのが一般的です。
任意後見とは
上記のとおり、法定後見の場合は、親に自分の後見人になって欲しいと希望している人がいたとしても、その人が後見人に選ばれるとは限りません。
希望している人に後見人になって欲しいのであれば、法定後見ではなく、任意後見を選択する必要があります。
任意後見とは、判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見人になって欲しい人の間で、代理にしてもらいたい法律行為を定めた任意後見契約を締結しておくという制度です。
実際に、認知症などで判断能力が衰えてしまった場合には、任意後見契約に基づいて、任意後見人が本人に代わって法律行為を行うことになります。
任意後見制度を利用すれば、親が認知症になる前に任意後見契約を締結してもらうことによって、親の希望する人を任意後見人に選任し、また、代理できる法律行為の範囲も決めておけます。
任意後見契約の効力発生までの実務
任意後見制度を利用して任意後見契約の効力が発生するまでには、以下の手順が必要です。
- 任意後見人となってもらう人を選ぶ
- 任意後見契約書を作成する
- 本人と任意後見人候補者との間で任意後見契約を締結する
- 判断能力低下後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
1. 任意後見人となってもらう人を選ぶ
任意後見契約を締結する前に、任意後見人になってもらう人を選んでおかなければなりません。
信頼できる人を選任する必要がありますが、もちろん相手にも断る自由があります。相手の了承を得ておく必要があります。
任意後見人になってもらうことを弁護士に依頼する方法もあります。
2. 任意後見契約を作成する
任意後見契約では、任意後見人が本人に代わって行える法律行為の範囲を決めておく必要があります。
任意後見人が行える法律行為は、大きく分けると財産管理と身上監護です。
財産管理とは、本人の資産や収支を管理することです。不動産、預貯金、有価証券などの資産の管理だけでなく、家賃や光熱費の支払いなどの支出の管理や税金の支払いなどの税務処理も委任することが可能です。
身上監護は、入院や手術などの医療や老人ホームなどの介護に関する契約の締結およびその手続などを委任することになります(具体的な事実行為としての介護までは委任できません。)。
任意後見人は、任意後見契約で定められていない法律行為を行うことはできないため、代理してもらいたい法律行為を漏れのないように定めておく必要があります。
3. 任意後見契約を締結する
任意後見契約書を作成したら、実際に、本人(委任者)と任意後見人候補者(受任者)との間で任意後見契約を締結する必要があります。
任意後見契約は、口頭で締結できません。必ず書面(任意後見契約書)を作成して締結する必要があります。
しかも、ただ書面にするだけではなく、公正証書で任意後見契約書を作成しなければなりません。
したがって、任意後見契約書を締結する際は、公証役場に行き、公証人に任意後見契約公正証書を作成してもらうことになります。
もちろん、いきなり公証役場に出向いて作成してもらうわけではなく、あらかじめ公証役場に連絡を入れて作成した任意後見契約書の案を送付しておき、契約締結当日を迎えるのが通常です。
4. 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする
任意後見契約を締結すれば、それだけで判断能力が低下した後に契約の効力が生じるわけではありません。
本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されて監督が開始されてはじめて任意後見契約の効力が発生します。
任意後見監督人選任の申立ては、本人(委任者)、任意後見人受任者、配偶者、四親等内の親族です。本人以外の場合は、原則として、本人の同意が必要となります。
任意後見監督人とは、任意後見人の代理行為を監督する人のことです。通常は、利害関係のない第三者である弁護士などから選任されます。
任意後見契約の注意点
任意後見契約は、法定後見と異なり、本人の意思を尊重できる制度です。ただし、いくつか注意しなければいけない点があります。
以下では、任意後見契約の注意点について説明します。
代理権の範囲の定め方に関する注意点
前記のとおり、任意後見人は、任意後見契約書に定められていない法律行為を本人に代わって行うことはできません。
そのため、任意後見契約書に不備や不測があると、いざというときに任意後見人が何もできないということになりかねません。
また、任意後見契約書の書き方があいまい・不明確であると、代理権の範囲について争いが起きるなどのトラブルが発生するおそれがあります。
したがって、任意後見契約書の代理権の範囲は、想定される法律行為を漏れのないように、かつ、明確に定めておく必要があります。
死後の事務に関する注意点
本人が亡くなると、任意後見契約は効力を失います。したがって、任意後見人がいても、本人が亡くなった後の遺産や遺品の管理などをしてもらうことはできません。
死後の事務も任意後見人に行ってもらいたい場合は、任意後見契約とともに死後事務委任契約を締結してカバーする必要があります。
取消権に関する注意点
本人が詐欺などにあって不利益な法律行為をしてしまった場合、法定後見の成年後見人であれば、本人に代わってその法律行為を取り消すことができます。
しかし、あえて任意後見を選択した本人の意思を尊重する趣旨から、任意後見人には取消権の代理が認められていません。
したがって、本人が詐欺などにあった場合には、別の方法で詐欺による法律行為を取り消すなどの措置をとる必要があります。
例えば、任意後見契約書に紛争処理の代理権を定めておいて、それに基づいて、取消権以外の法律構成を使って裁判などで争うことになります。
まとめ
親が認知症になる前に、親の希望を叶える方法として、任意後見契約を締結する方法が有効です。
しかし、任意後見契約書は、漏れなく明確に作成しなければならず、本人の希望を確実に反映させるのは容易ではありません。
当事務所でも遺産相続に関する各種のご相談を承っています。任意後見契約でお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。