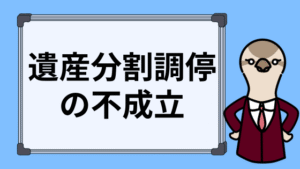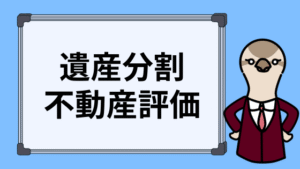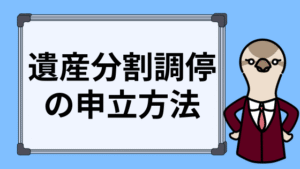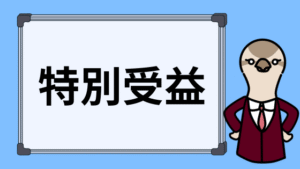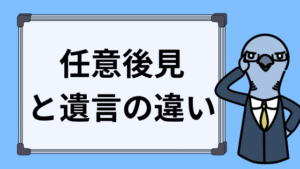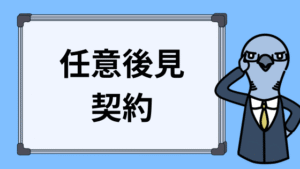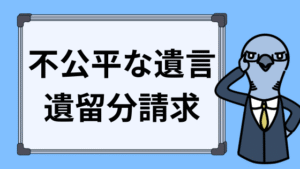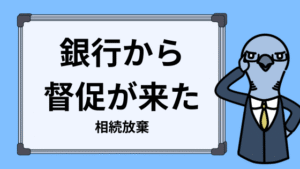遺産分割調停の管轄はどこ?申立先を間違えないための基本知識 ─ 裁判所選びで迷わないために知っておくべきルール
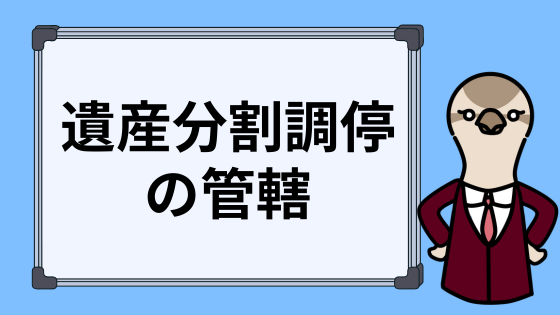
遺産分割調停を検討する際、「どの家庭裁判所に申し立てればいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
家族や親族間で話し合いがまとまらず、円満な遺産分割が難しいとき、多くの人が家庭裁判所の調停手続きを利用します。
しかし、どこの家庭裁判所でも受け付けてもらえるわけではありません。法律で定められた「管轄」のルールがあることをご存知でしょうか。
このルールを理解せずに誤った裁判所に申し立ててしまうと、手続きがやり直しになったり、余計な時間と手間がかかったりする可能性があります。
この記事では、遺産分割調停をスムーズに進めるために不可欠な、管轄の基本知識をわかりやすく解説します。
遺産分割調停の「管轄」とは何か?
「管轄」とは、ある事件をどの裁判所が扱うかを決めるルールのことです。
この管轄には、職分管轄と土地管轄があります。職分管轄とは、事件の性質や内容に応じて決められる管轄のことです。一方、土地管轄とは、裁判所の所在地に応じて決められる管轄です。
日本全国には多数の家庭裁判所がありますが、どこでも好きな裁判所に遺産分割調停を申し立てられるわけではありません。
管轄のない裁判所に申立てをすると、手続が振り出しに戻ってしまうリスクがあります。
遺産分割調停の場合、一般的な民事訴訟の管轄ルールとは異なる特別な規定が設けられています。
具体的に言うと、遺産分割調停を申し立てるべき管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です(家事事件手続法245条1項)。
管轄を間違えた場合
もし管轄のない裁判所に申立てをしてしまうと、どうなるのでしょうか。
この場合、原則としては、裁判所が管轄外と判断すれば、遺産分割調停の手続は開始されず、正しい管轄裁判所へ事件が移送されことになります。
移送になった場合、移送には時間がかかるため、相続人間の関係が悪化している場合には大きな不利益となる可能性もあります。
そのため、申立前に必ず「自分のケースではどの裁判所が管轄するのか」を確認しておくことが重要です。
以下では、遺産分割調停における正しい管轄である「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」について説明します。
当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)
どこを管轄の裁判所とするかは、当事者間の合意で決めることができる場合があります。当事者間で管轄を決める合意のことを「管轄の合意」と言い、この管轄の合意で管轄を決めることを「合意管轄」と言います。
遺産分割調停も、当事者間の合意によって管轄を決めることができるとされています。
ここで言う「当事者」とは、相続人のことです。相続人全員が合意していれば、その合意で決められた裁判所を管轄裁判所とすることができます。
例えば、遺産分割調停の申立人Aは東京に住んでおり、相手方の相続人Bは大阪に住んでいた場合でも、AとBが、利便性を考えて、名古屋家庭裁判所を管轄裁判所とする合意をすれば、名古屋家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
このように、管轄の合意は、当事者全員が円満な解決を望んでおり、手続きの利便性を最優先したいような場合には、有効な制度です。
ただし、管轄の合意をする場合には、以下の点に注意が必要です。
管轄合意の注意点①相続人全員の合意が必要
管轄の合意は、相続人「全員」が合意していなければ効力を生じません。
一人でも合意に反対すれば合意管轄は成立しないため、事前に十分な話し合いをしておく必要があります。
管轄合意の注意点②家庭裁判所は変更できない
管轄の合意によって変更できるのは、裁判所の場所だけです。家庭裁判所が管轄であることは変えられません。
したがって、管轄の合意をしたからといって、申し立てる裁判所を家庭裁判所から地方裁判所や簡易裁判所に変えることはできません。
管轄合意の注意点③書面(管轄合意書)の作成が必要
管轄の合意は、書面でしなければ効力を生じません(家事事件手続法245条2項、民事訴訟法11条2項)。ただ口頭で管轄の合意をしただけでは、管轄の合意は効力を生じないのです。
合意によって管轄裁判所を決める際には、相続人全員との間で書面(管轄合意書)を取り交わしておく必要があります。
この管轄合意書は、実際に遺産分割調停を申し立てる際に、管轄の合意をしたことの証拠として家庭裁判所に提出しなければなりません。忘れずに作成しておきましょう。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
相続人間における管轄の合意がない場合には、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
これは、調停が話し合いの手続きであるため、申立人だけでなく、相手方の利便性も考慮されているためです。申立人自身の住所地や、被相続人の最後の住所地ではありませんので、この点をまず押さえておくことが重要です。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 被相続人(亡くなった方):東京都在住で死亡
- 相続人A(申立人):大阪市在住
- 相続人B(相手方):名古屋市在住
この場合、申立人Aが遺産分割調停を起こしたいと思っても、自分の住所地である大阪家庭裁判所に申し立てることはできません。原則として、相手方Bの住所地である名古屋家庭裁判所に申立てる必要があります。
相手方が複数人いる場合
相手方(相続人)が複数人いる場合、「一体どこに申し立てればよいのか」と混乱することがあるかもしれません。しかし、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申立てをすればよいだけです。
つまり、相手方が複数人いる場合には、その複数人の相手方の中からどこでも好きな家庭裁判所を選ぶことができるということです。
例えば、相続人Aは東京都在住、相続人Bは大阪市在住、相続人Cは福岡市在住のケースで、Aが遺産分割調停を申し立てる場合、Aは、大阪家庭裁判所と福岡家庭裁判所のどちらに申立てをしてもよいことになります。
相続人が複数人いる場合には、自身の交通費や移動の負担を考慮して、より便利な場所を選ぶことができるので、申立人にとって非常に有利になる場合があります。
不動産など重要な遺産がある場合
遺産(相続財産)の中に、不動産など重要な財産がある場合、その不動産などがある地域の家庭裁判所を選択した方がよいのではと考える方もいるかもしれません。
しかし、前記のとおり、遺産分割調停における管轄のルールは、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
このルールは、不動産など重要な遺産がある場合でも変わりません。
したがって、重要な財産があっても、申し立てるべき管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」のどちらかです。
もっとも、遺産分割のために、管轄の法務局に確認をとったり、現地確認をしたりしなければならないこともあるため、不動産の所在地に近い裁判所で手続した方が効率的なケースもあります。
もし複数の候補がある場合は、利便性を考慮して申立先を選ぶのが望ましいでしょう。
相手方が海外在住の場合
相手方相続人の一部が海外に在住している場合、それ以外の相手方相続人が国内在住であれば、その国内在住の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをするのが通常です。
相手方が全員海外在住の場合には、その中に日本国内に住民票を持っている相手方がいれば、その住民票の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることが可能です。
相手方が海外在住の場合は、要する手続きも複雑になるため、弁護士に相談することを検討してください。
遺産分割審判との管轄の違い
遺産分割調停でも話がつかなかった場合、最終的に遺産分割審判によって、どのように遺産分割するのかを裁判所に決めてもらうことになります。
この遺産分割審判は、遺産分割調停と管轄が異なります。遺産分割審判の場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所です。
遺産分割調停で話がつかなかった場合、審判に移行します。この際、調停をしていた家庭裁判所で審判も行われるのが通常ですが、まれに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあります。
なお、遺産分割では、必ず調停を先に申し立てなければならないとする原則(調停前置主義)の適用はありません。
そこで、いきなり遺産分割審判を申し立てることも可能とされています。ただし、遺産分割調停を経ずに審判を申し立てた場合、調停に付されるのが通常です。
調停に付される場合、調停の管轄裁判所に移送されるのが原則ですが、移送をせずに、審判を申し立てた裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所)のまま調停も行われる(自庁処理される)ことがあります。
まとめ
遺産分割調停の管轄裁判所は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
一見すると単純ですが、相続人が多数に及んだり、相手方が海外に住んでいたり、不動産が存在する場合など、判断が難しいケースも少なくありません。
申立先を誤ると解決までの時間が長引き、家族関係がさらに悪化する恐れもあります。
管轄で間違いを犯さないためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、法令の解釈だけでなく、実務上の裁判所の運用も踏まえて最適な申立先を提案してくれるでしょう。