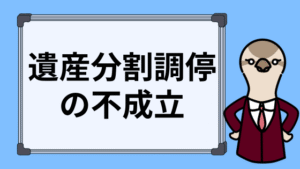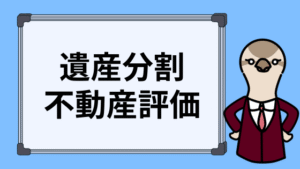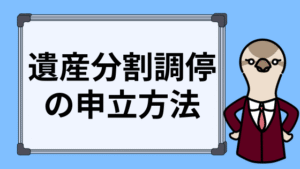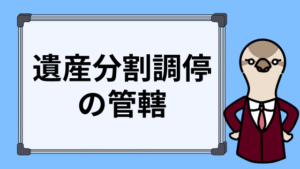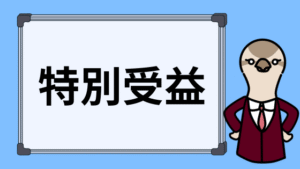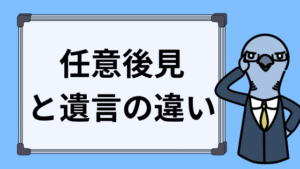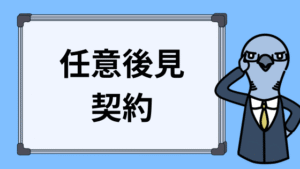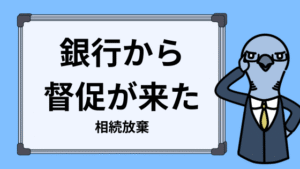「全財産を長男に」という遺言は不公平!「遺留分」を請求する手続きと時効を解説
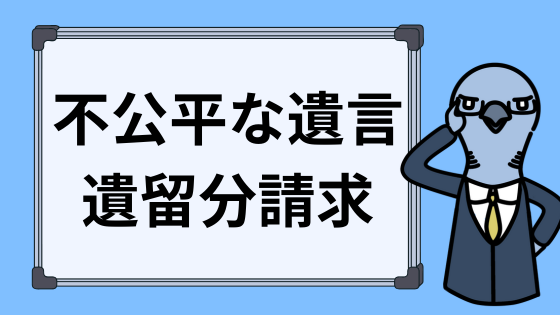
「全財産を長男に」という他の相続人にとっては不公平な遺言が作成されているようなケースはよくある話です。
この場合、次男や長女など他の相続人は一切遺産を受け取れないのでしょうか?
実は、そのようなことはありません。他の相続人も、一定の範囲で遺産を受け取ることが可能です。なぜなら、相続人には「遺留分」と呼ばれる権利が保障されているからです。
本記事では、この遺留分とは何か、遺留分を請求するにはどのような手続をとればよいのか、遺留分の請求に時効はあるのかなどをご説明します。
「全財産を長男に」という不公平な遺言が作成されていて困っている方がいらっしゃいましたらご一読ください。
「全財産を長男に」という不公平な遺言も有効?
まず、「全財産を長男に」という次男や長女など他の相続人にとって不公平な遺言が、そもそも有効なのかという問題があります。
法定相続人とは?
遺産相続で遺産を遺して亡くなられた人のことを「被相続人」と言います。
被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
被相続人の「子」は、第1順位の相続人となります(民法887条)。
したがって、他に被相続人の直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など)や兄弟姉妹がいても、子が相続人になります。
ただし、配偶者だけは常に相続人になります。そのため、子と配偶者がいる場合には、子と配偶者がともに相続人となります。
法定相続分とは?
相続人が複数人いる場合、誰がどのくらいの遺産を受け取れるのかについての基本的な割合も、民法で決められています。これを「法定相続分」と言います。
子が複数人いる場合、それぞれの子の相続分は、頭数で割って決めることになります。したがって、例えば、子が3人いれば、それぞれ3分の1ずつが法定相続分となります。
配偶者がいる場合には、子と配偶者が相続にとなります。法定相続分は、子が2分の1、配偶者が2分の1です。
子が複数人いる場合には、子の割当分である2分の1を頭数で割って決めます。
したがって、例えば、子が3人と配偶者がいる場合には、配偶者は2分の1、子は、2分の1を3人で分け合うので、それぞれ6分の1ずつということになります。
不公平な遺言の有効性
「全財産を長男に」という遺言は、もし、被相続人の長男以外にも子や配偶者がいた場合、その長男以外の子や配偶者の法定相続分を無視していることになります。
そうすると、他の相続人にとっては不公平です。このような他の相続人の法定相続分を侵害する遺言は無効になるのではないかとも思えます。
しかし、遺言は、遺産を遺した被相続人の意思です。したがって、遺産相続においては、最も尊重されるべきものです。
そのため、「全財産を長男に」という不公平な遺言も有効となります。遺言による相続分の指定(指定相続分)は、法定相続分よりも優先されるのです。
不公平な遺言があっても遺産分割はできる?
不公平な遺言があった場合、他の相続人としてはどのような手段をとることができるのでしょうか?
1つの方法としては、遺産分割があります。遺言がある場合でも、相続人全員で話し合って、遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。
したがって、長男と他の相続人とで話し合って、遺言と異なる遺産の配分を決めることができます。
とは言え、長男が話し合いに応じなければ、遺産分割はできません。
遺産分割ができない場合、もはや他の相続人は諦めるしかないのかと言うと、そうではありません。他の相続人には、「遺留分」を主張するという手段が残されています。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
遺留分とは、相続人(なお、被相続人の兄弟姉妹を除きます。)に保障されている最低限度の遺産取得分です。
不公平な遺言によって法定相続分を侵害された場合でも、兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分に相当する分だけは、遺産を受け取ることができるのです。
「全財産を長男に」という不公平な遺言があった場合でも、次男、長女、配偶者など他の相続人は、全財産を取得した長男に対して遺留分を主張することができます。
具体的には、遺留分を侵害している相続人などに対して、遺留分を侵害する額の金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
なお、遺留分侵害額請求は、2019年(令和元年)7月1日に開始された相続について適用されます。
2019年(令和元年)6月30日以前に開始された相続については、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることになります。
遺留分侵害額の計算
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするには、まず、遺留分侵害額を計算しておく必要があります。遺留分侵害額の計算は、若干複雑です。
1. 個別的遺留分の算定
それぞれの相続人の遺留分の割合(総体的遺留分)は、以下のとおり民法で決められています。
- 直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1
- それ以外の場合は、2分の1
この総体的遺留分に、法定相続分を乗じて、個別的遺留分を算出します。
例えば、配偶者と子3人がいる場合は、以下のようになります。
配偶者:法定相続分2分の1 × 総体的遺留分2分の1 = 4分の1
子:法定相続分6分の1 × 総体的遺留分2分の1 = 12分の1ずつ
2. 遺留分侵害額算定の基礎財産
遺留分侵害額を計算するには、算定の基礎となる遺産の金額を算出しておく必要があります。
基礎財産は、相続開始時に被相続人が有していた資産(積極財産)に、まず、生前贈与した財産をプラスします。そして、そこから、相続開始時に被相続人が負っていた負債(相続債務)をマイナスして算出します。
基礎財産 = 相続開始時に被相続人が有していた資産(積極財産)+ 生前贈与した財産の額 - 相続開始時に被相続人が負っていた負債(相続債務)
3. 特別受益・生前贈与の控除
遺留分侵害額を請求する相続人が、被相続人から特別受益に該当する利益を得ていたり、生前贈与を受けていたりした場合には、これらも考慮しなければ、かえって不公平になってしまいます。
そのため、遺留分侵害額を計算する場合には、遺留分侵害額を請求する相続人が受けていた特別受益や生前贈与の額を控除して計算することになります。
また、遺留分侵害額を請求する人が、相続によって何らかの財産を受け継いだり、または、何らかの負債を背負うことになったりした場合には、それも考慮されます。
4. 遺留分侵害額の算出(まとめ)
上記の個別的遺留分に基礎財産を乗じ、そこから特別受益や生前贈与額を控除して、遺留分侵害額を算出します。具体的には、以下の計算式になります。
遺留分侵害額 = 個別的遺留分額 × 基礎財産 - 遺留分侵害額を請求する人が受けていた特別受益や生前贈与の額 - 相続によって受け継いだ資産の額 + 相続によって負担することになった負債の額
遺留分侵害額請求の手続
遺留分侵害額を請求する権利は、形成権と考えられています。
つまり、遺留分侵害額を請求するという意思表示をすれば、それだけで、遺留分侵害額を請求できる金銭債権が発生するということです。
したがって、遺留分侵害額請求には、特別な方式はありません。遺留分侵害額を請求する意思表示をすればよいだけです。
遺留分を侵害している相続人等に対して、遺留分侵害額の請求書を、内容証明郵便で郵送するのが一般的でしょう。
配達証明も付けておくと、相手方に配達されたことも証拠として残しておけるので、より確実です。
もっとも、これはあくまで形式的な話です。
もちろん、請求書は郵送しておかなければいけません。しかし、相手方が遺留分侵害額請求を認めないということもあります。
その場合には、請求書を送るだけでは解決できません。交渉を行い、最終的には、訴訟によって遺留分侵害額を請求する必要があります。
遺留分侵害額請求の訴訟は、相続に関わるものではありますが、家庭裁判所ではなく、簡易裁判所または地方裁判所に提起します。
請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求の消滅時効と除斥期間
遺留分侵害額請求には期限があります。いつまででも可能であるというものではありません。
具体的に言うと、遺留分侵害額請求は、以下の場合に請求できなくなってしまいます。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年を経過した場合(消滅時効)
- 相続の開始から10年を経過した場合(除斥期間)
消滅時効の期間は、相続開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年しかありません。
もっとも、この期間内に、遺留分侵害額を請求する意思表示を1度でもしておけば、時効で消滅したり、除斥期間で請求できなくなったりすることはなくなります。
したがって、前記のとおり、早めに配達証明付きの内容証明郵便で遺留分侵害額の請求書を郵送しておいた方がよいでしょう。
ただし、遺留分侵害額請求は、あくまで遺留分侵害額を請求する形成権を行使しているにすぎません。
遺留分侵害額請求によって発生する具体的なお金を支払ってもらう権利は、別途、時効によって消滅することがあります。
具体的には、以下の場合に時効によって消滅します。
- 遺留分侵害額に相当する金銭を請求できることを知った時から5年間
- 遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる時から10年間
したがって、相手方との話し合いに決着が着かない場合には、時効の期間内に訴訟を提起しなければなりません。
遺留分侵害額請求をした後にも時効が存在する点は留意が必要です。
遺留分減殺請求について
前記のとおり、2019年(令和元年)6月30日以前に開始された相続については、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求をすることになります。
遺留分減殺請求の場合、遺留分侵害額請求と異なり、金銭の請求ではなく、相続財産そのものの一部を請求することになります(ただし、実際には、金銭で解決する場合が少なくありません。)。
手続や時効などについては、遺留分侵害額請求と基本的には同じですが、調停が行われるなどの違いもあります。
まとめ
「全財産を長男に」という不公平な遺言であっても、被相続人の意思である以上、有効となります。
全財産を受け継いだ長男との話し合いが上手くいかないときには、長男に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。
もっとも、遺留分侵害額請求は、侵害額の計算も複雑です。訴訟になれば、法的な専門知識も必要となってきます。
確実に遺留分侵害額請求をしたいということであれば、やはり、最初の段階から弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。