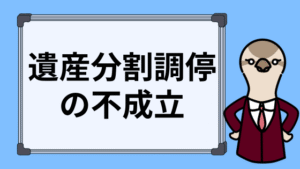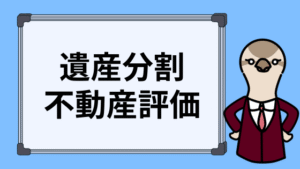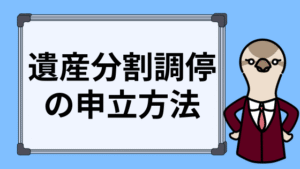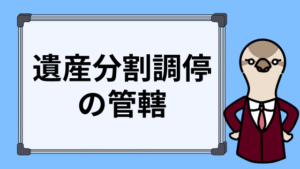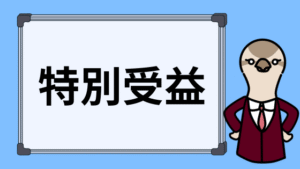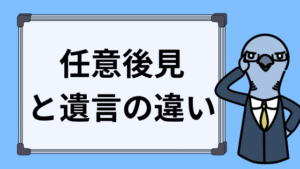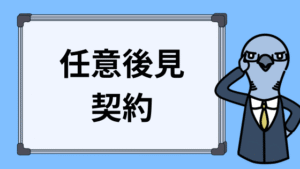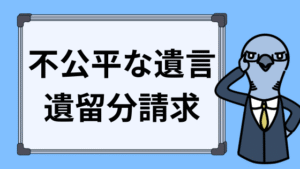【弁護士解説】故人の銀行口座が凍結!遺産分割前の「預貯金の仮払い制度」の上手な使い方
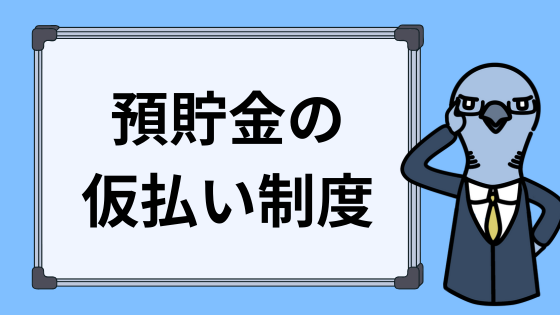
相続が開始されたことを銀行が知った場合、故人の銀行口座は凍結されてしまいます。
いったん凍結されると、遺産分割が終わるまで相続人でも自由に引き出すことはできなくなるのが原則です。
もっとも、遺産分割前の「預貯金仮払い制度」を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を引き出すことが可能となります。
本記事では、この遺産分割前の預貯金仮払い制度とはどのような制度なのか、その上手な使い方などについて解説します。
遺産分割前に預貯金の払戻しをしたいとお考えの方や預貯金仮払い制度の利用をお考えの方は、ご一読ください。
故人の銀行口座から預金を引き出すことはできない?
遺産相続で遺産を遺して亡くなられた故人のことを「被相続人」と言います。
被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
銀行口座に入っている預金は、相続財産です。
厳密に言うと、銀行口座に入っているお金ではなく、銀行口座からお金を払い戻す権利が、相続財産となります。預金払戻請求権、預金債権などと呼ばれています。
この故人の預金払戻請求権は、相続人に引き継がれます。
預金の準共有
相続人が1人であれば、その相続人が全額を引き継ぎます。
しかし、相続人が複数人いる場合、この預金払戻請求権は、遺産分割によってそれぞれの相続人への帰属が確定するまで、複数人の相続人(共同相続人)全員の準共有になると考えられています(最高裁判所大法廷平成28年12月19日判決など)。
準共有とは、共同相続人全員で預金払戻請求権を有しているということです。
そのため、遺産分割が終わるまで、相続人各自でそれぞれ勝手に預金を引き出すことはできません。
預金口座の凍結
上記のとおり、預金払戻請求権は、共同相続人全員の準共有となり、各相続人が単独で引き出すことはできません。
この預金払戻請求権の取扱いに対応して、銀行側は、相続紛争を回避するために、銀行口座の名義人である被相続人が亡くなったことを知った場合、その預金口座を凍結します。
したがって、相続人が複数人いる場合、遺産分割を終わらせてからでなければ、相続人であっても、故人の預金を引き出すことができないのが原則なのです。
遺産分割前に預金を引き出す方法
遺産分割前に各相続人が単独で預金を引き出すことはできないのが原則です。
もっとも、故人の葬儀費用などのために、故人の預金口座からお金を引き出す必要性が生じることもあり得ます。
そこで、遺産分割前に預金を引き出す方法について考える必要があります。
共同相続人全員の同意がある場合
遺産分割がすべて完了していないときでも、共同相続人全員が預金の引き出しに同意している場合には、預金を引き出すことは可能です。
この場合には、共同相続人のうちの代表者が、他の共同相続人全員の同意書や委任状を銀行に提出して、預金を引き出すことになります。
ただし、全員の同意が必要なので、1人でも反対する人がいれば、この方法はとれません。
銀行の便宜払いを利用する方法
一部の銀行では、故人の葬儀費用などのために必要な場合に限り、相続人による預金の引き出しを認める「便宜払い」をしてくれるところもあります。
ただし、相続紛争に巻き込まれるリスクがあるため、どこの銀行でも応じてくれるわけではありません。
預貯金の仮払い制度を利用する方法
上記のとおり、遺産分割前に故人の預金を引き出すのは、容易ではありません。しかし、必要性があることも事実です。
そこで、2019年(令和元年)の民法改正によって、預貯金の仮払い制度が設けられました。
遺産分割前に故人の預金を引き出す方法としては、この預貯金の仮払い制度が最も確実でしょう。
以下では、この預貯金仮払い制度について解説します。
預貯金仮払い制度とは?
民法909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
預貯金仮払い制度とは、家庭裁判所の許可がなくても、遺産分割前に一定範囲の預貯金を払い戻すことができるという制度です(民法909条の2)。
前記のとおり、相続人が複数人いる場合、故人の預金を引き出すことは容易ではありませんでした。しかし、葬儀費用などのために引き出す必要性があることも事実です。
そこで、相続人の資金需要に応えるために設けられたのが、この預貯金仮払い制度なのです。
預貯金仮払い制度で引き出せる金額
預貯金仮払い制度を利用した場合、いくらでも引き出せるわけではありません。引き出せる金額の上限は決まっています。
具体的には、以下の金額のうち低い方の金額が上限とされています。
- 相続開始時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1
- 150万円
引き出せる金額の具体例
例えば、相続開始時の預金残高が1200万円、相続人として子2人と配偶者がいた場合について考えてみます。
この事例の場合、子2人の法定相続分は4分の1ずつ、配偶者の法定相続分は2分の1です。
配偶者が預貯金仮払い制度で預金を引き出す場合、「相続開始時の預金残高1200万円×法定相続分2分の1×3分の1=200万円」よりも150万円の方が金額として低いので、150万円が引き出しの上限額となります。
子の1人が預金を引き出す場合は、「相続開始時の預金残高1200万円×法定相続分4分の1×3分の1=100万円」の方が150万円よりも金額として低いので、100万円が引き出しの上限額となります。
複数の銀行口座がある場合
故人の預金口座が複数あるという場合もあります。
この場合、それぞれの口座ごとに、前記の上限が設定されることになります。したがって、預金口座が複数ある場合には、引き出せる金額が150万円以上になることもあります。
例えば、A銀行口座とB銀行口座に預金があった場合、それぞれの口座から「相続開始時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1」または「150万円」のいずれか低額な方の金額まで引き出せるということです。
ただし、同じ銀行の別支店の口座が複数ある場合は、全部が1個の口座として扱われるので、口座ごとに上限額が設定されるわけではありません。
預貯金仮払い制度の手続
預貯金仮払い制度を利用するために、家庭裁判所の手続などを行う必要はありません。故人の預金のある銀行などに行って、預貯金仮払いの手続をすればよいだけです。
もっとも、各銀行などによって手続や必要となる提出書類は異なります。
あらかじめ対象となる銀行などに問い合わせをして、手続や必要書類について確認をしておく必要があります。
預貯金仮払い制度を利用した場合の遺産分割
預貯金仮払い制度を利用すると、相続財産である預金(払戻請求権)の一部を遺産分割前に取得したのと同じことになります。
そのため、預貯金仮払い制度によって預金を引き出した場合、その引き出した金額に相当する預金払戻請求権を遺産の一部分割によって取得したものとみなされることになります。
したがって、遺産分割においては、当然、その引き出した金額はすでに受け取ったものとして差し引かれることになります。
預貯金仮払い制度の上手な利用方法と注意点
預貯金仮払い制度は、共同相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に故人の預金を引き出すことができる非常に便利な制度です。しかも、手続も難しくありません。
もっとも、この預貯金仮払い制度を上手に利用するためには、以下の点に注意しておく必要があります。
- 相続財産を処分したことになるため、相続放棄ができなくなる。
- 他の相続人との間で預金の引き出しについてトラブルになる可能性がある。
特に、相続財産に負債が含まれている場合、預貯金払戻し制度を利用すると、後で相続放棄することができなくなってしまうことには注意しておきましょう。
また、他の相続人とのトラブルにならないように、預貯金仮払い制度を使うときは、あらかじめ他の相続人には連絡をしておいた方がよいでしょう。
なお、当然のことですが、預貯金仮払い制度を利用した後、正式に遺産分割をしなければいけません。
後の遺産分割も含めて預貯金仮払い制度を利用すべきかどうかなどで迷っている場合には、弁護士に相談するのも1つの方法です。