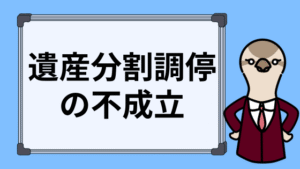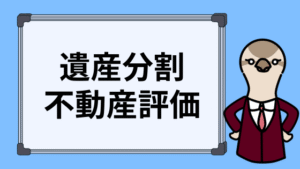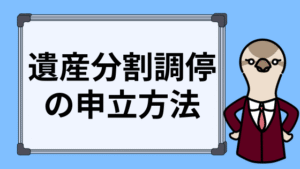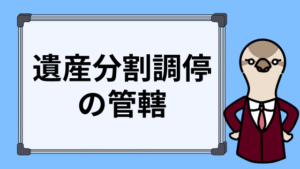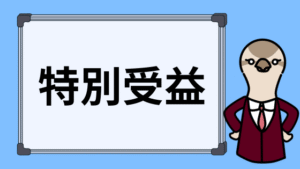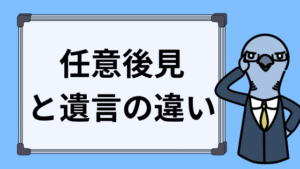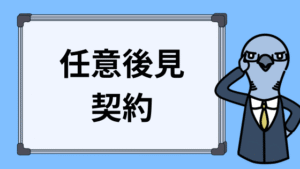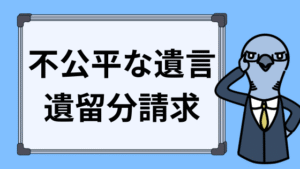遺言書を勝手に開封してしまった!その遺言書は無効になる?罰則は?
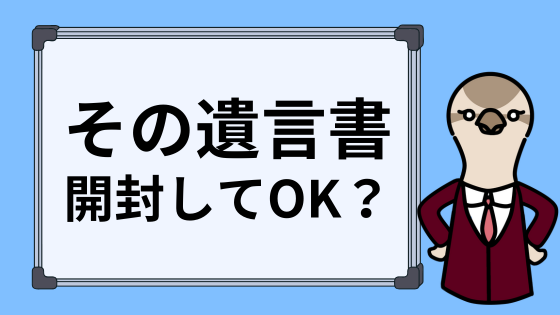
遺言書が封をされている場合、これを勝手に開封してはいけません。とはいえ、つい開封してしまったというケースもあるでしょう。
本記事では、遺言書を勝手に開封してしまった場合、その遺言書は無効になってしまうのか、罰則はあるのかなどについて詳しく解説していきます。
遺言書を勝手に開封してしまってお困りの方などいらっしゃいましたら、ご一読ください。
なぜ遺言書を勝手に開封してはいけないのか?
遺言書は、封筒などに入れられて、封印されているのが通常です。
勝手に開封されてしまうと、偽造、改ざん、すり替えなどをされる危険性があります。そうなると、中に入っていた遺言書が、はたして本物の遺言書なのかどうかが分からなくなってしまいます。
そのため、遺言書が封印されている場合、これを勝手に開封してはいけないとされているのです。
もっとも、逆に言うと、遺言書が開封されても、改ざんや偽造のおそれがなく、本当の遺言書であるかどうかが判別できるのであれば、勝手に開封されても問題はないということになります。
勝手に開封されても問題ないかどうかは、遺言書がどのような方式で作成されたものかによって異なります。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、遺言をする人(遺言者)が、自筆(手書き)で遺言書を作成する方式の遺言です。
自筆証書遺言は、特別な手続もなく作成できるため、最も簡便な方式です。そのため、最も多く利用されている遺言の方式です。
もっとも、自筆証書遺言書は、遺言者のみが関与して作成する方式です。公正な第三者が遺言書の内容を記録しておいてくれるわけではありません。
そのため、封印されていた自筆証書遺言書が開封されてしまうと、中に入っていた遺言書が本物であるかどうかを判別することが難しくなってしまいます。
そこで、自筆証書遺言書は、勝手に開封してはならず、家庭裁判所の検認手続において開封しなければならないものとされています。
検認手続とは?
検認手続とは、遺言書の偽造などを防ぐため、家庭裁判所において、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を記録してもらう手続です。
封印されている遺言書は、この検認手続で、相続人などの立ち合いのもとで、家庭裁判所において開封することになります。
ただし、あくまで遺言書の形状などを確認するための手続ですので、検認手続をしたからと言って、その遺言書が有効なものかどうかまで判断されるわけではありません。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合
上記のとおり、自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続において開封する必要があるのが原則です。
もっとも、自筆証書遺言書であっても、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は別です。
自筆証書遺言書保管制度とは、一定の様式で作成された自筆証書遺言書を法務局が保管してくれるという制度です。
法務局が遺言書を保管しておいてくれるので、遺言書が本物であることを担保することができます。
そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、自筆証書遺言書であっても、検認手続は不要となり、検認手続以外で開封してしまっても問題はありません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証役場で、証人2人立会いのもとに、公証人に遺言書を公正証書として作成してもらうという方式の遺言です。
公証役場に出向く手間や公証人に支払う費用などがかかりますが、法律の専門家である公証人が、公的な書類である公正証書として作成してくれるため、確実性があります。
また、公正証書遺言書は3通作成され、謄本2通は遺言者に渡されますが、正本は公証役場で保管してもらえます。したがって、遺言書が本物であることを担保することができます。
そのため、公正証書遺言の場合も、検認手続は不要であり、検認手続以外で開封してしまっても問題はありません。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言とは、完全に封印した遺言書を公証人と証人2人に確認してもらい、封印されているものであることを記録してもらうことによって、遺言の内容を完全に秘密にできるという方式の遺言です。
秘密証書遺言は、自ら作成しなければならない上に、公証役場に出向き公証人に費用を支払わなければなりません。
しかも、公正証書遺言と異なり、遺言書を公証役場で保管してくれません。
したがって、秘密証書遺言の場合には、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合と同様、勝手に開封してはならず、家庭裁判所の検認手続において開封しなければならないものとされています。
勝手に開封してはいけない遺言書の種類
以上のとおり、法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言書と公正証書遺言書は、検認手続が不要となり、検認手続以外で開封してしまっても問題ありません。
開封してしまっても、法務局や公証役場に行けば、開封された遺言書が本物かどうか容易に確認できるからです。
これに対して、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は、勝手に開封してはならず、検認手続において開封しなければなりません。
勝手に開封すると遺言書は無効になる?
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を勝手に開封してしまった場合、その遺言書は無効になってしまうのでしょうか?
結論から言うと、無効にはなりません。
遺言は、遺言を残して亡くなった人の意思表示です。最大限尊重されるべきものです。開封されただけで無効になってしまうのでは、遺言者の意思が無になってしまいます。
そのため、仮に勝手に開封してしまったとしても、遺言書が無効となることはないのです。
遺言書の有効性を争われる可能性
上記のとおり、勝手に開封してしまったからと言って、遺言書が無効になるわけではありません。
もっとも、勝手に開封してしまっているので、中に入っていた遺言書が本物なのかどうか、偽造されたものではないのかどうかを判断するのが難しくなってしまいます。
そのため、遺言書を勝手に開封してしまうと、その遺言書が有効なものなのかどうかが相続人間で争われる可能性があります。
例えば、開封された遺言書の内容が自分にとって不利益なものである相続人などが、遺言書は偽物であるなどと言って、遺言の無効を争ってくることも考えられます。
勝手に開封しても、それだけで遺言書が無効になることはありませんが、相続人間で遺言書の有効・無効が争われるきっかけになってしまう可能性はあるのです。
検認手続は不要になる?
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を勝手に開封してしまった場合でも、検認手続をしないでよくなるわけではありません。
したがって、開封してしまったとしても、家庭裁判所で検認手続を行いましょう。
勝手に開封すると罰則を課される?
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書を勝手に開封してしまった場合、罰則が課されます。
具体的に言うと、検認手続を行わずに遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
過料とは、行政罰として強制的に取り立てられる金銭です。刑罰ではないので、前科が付くようなものではありません。
なお、公正証書遺言書については、開封しても罰則はありません。
また、法務局による遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言の場合は、そもそも封印されていないので、罰則の問題は生じません。
まとめ
以上のとおり、遺言書を勝手に開封してしまったからと言って、遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を勝手に開封してしまうと、相続人間で遺言書の有効性についてトラブルになったり、罰則を受けたりするおそれはあります。
したがって、封印された遺言書を発見しても、むやみに開封しないように気を付けましょう。封印された遺言書の取扱いが分からない場合には、開封する前に弁護士に相談してみましょう。