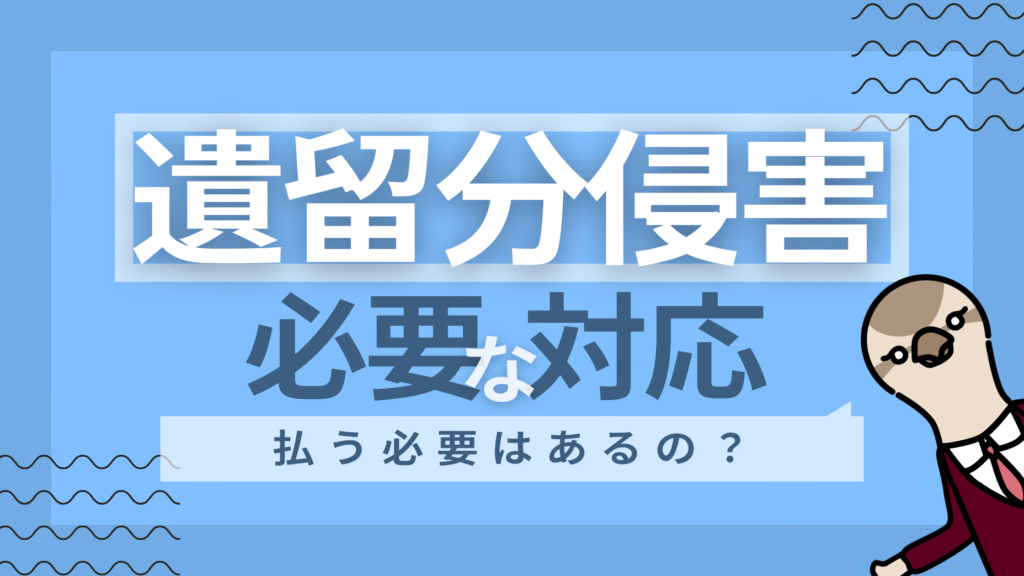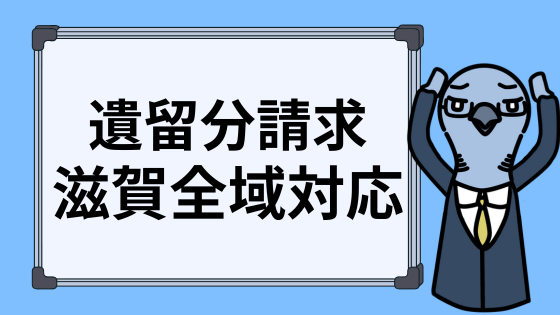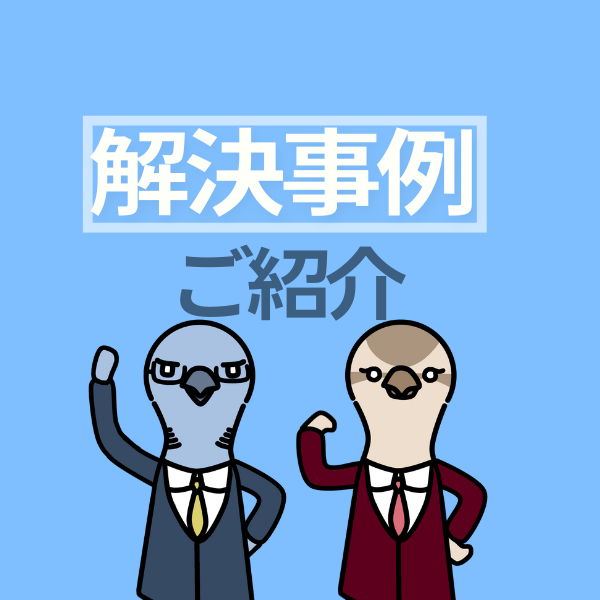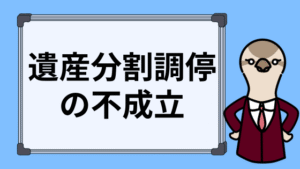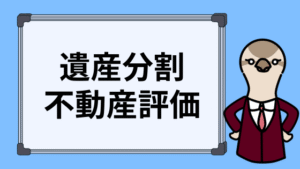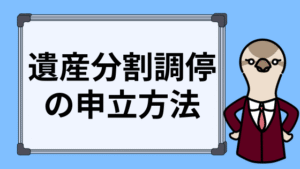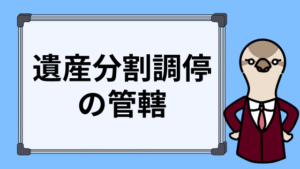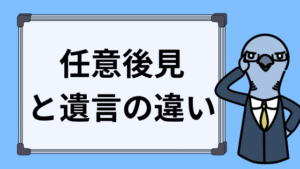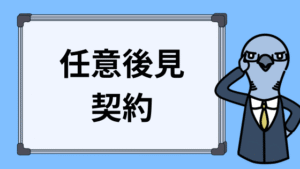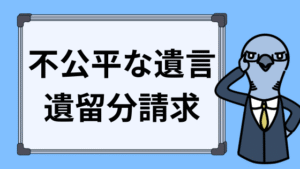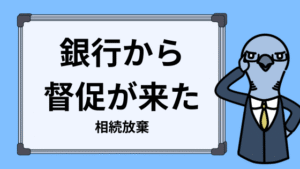「特別受益」とは?遺産分割における具体例と注意点を徹底解説 ─ 生前贈与や学費援助は相続分にどう影響するのか
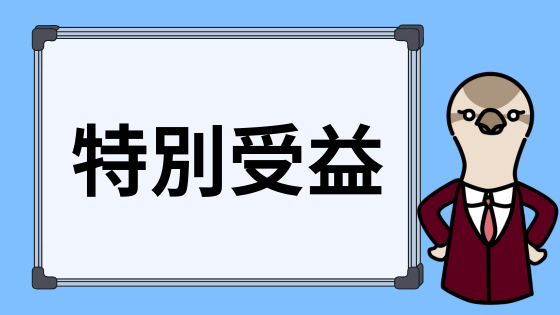
「生前に多額の援助を受けていた相続人がいるが、その分はどう扱うのか?」
「学費や住宅購入の援助は特別受益に含まれるのか?」
相続をめぐるトラブルの中でも、しばしば問題になるのが「特別受益」です。この記事では、特別受益の基本概念から具体例、遺産分割における影響、そして注意すべきポイントまで徹底解説します。
▼弁護士監修の相続コラム▼
特別受益とは?
ある人が亡くなった場合、その人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。遺産を遺して亡くなった人のことを被相続人と言います。
もっとも、被相続人の生前に、その被相続人から相続人のうちの特定の人が、学費の援助など生前贈与を受けているような場合があります。
贈与されることにより、その財産は受け取った相続人の財産となりますから、実際に相続が開始された時には、もはや相続財産ではありません。したがって、遺産分割の対象にもならないのが原則です。
しかし、たとえ生前に行われた贈与などであっても、他の相続人との間で不公平を生じる可能性もあります。
そこで、この生前贈与などを受けた相続人とそうでない相続人との間の公平を図るために設けられている制度が「特別受益」です。
すなわち、特別受益とは、共同相続人の中で特定の人が被相続人から生前に特別な利益を受けていた場合、その利益を遺産分割において考慮し、相続分を調整する制度です(民法903条)。
特別受益による調整:持ち戻し計算
前記のとおり、特別受益がある場合、遺産分割において調整されます。
それでは、どのように調整されるのかというと、特別受益を受けた相続人について、その利益を遺産に加算した上で相続分を計算し、すでに受けた利益を差し引くという方法で調整されます。
この計算のことを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
特別受益の持ち戻し計算は、以下の手順で行います。
- 全体の相続財産に、生前贈与(婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本のためのものに限る)の額を加算して「みなし相続財産」を算出する
- みなし相続財産を法定相続分で配分して、各共同相続人それぞれの「一応の相続分」を算出する
- 生前贈与・遺贈を受けた相続人の一応の相続分から、生前贈与・遺贈の額を差し引く
持ち戻し計算の例
例えば、遺産総額が3000万円、相続人が子ども2人(AとB)、Aは生前に1000万円を贈与されていた場合の持ち戻し計算は、以下のとおりです。
- 遺産総額3000万円に生前贈与額1000万円を加算=みなし相続財産額は4000万円
- 4000万円をABの法定相続分2分の1ずつで配分=一応の相続分は、それぞれ2000万円ずつ
- Aの一応の相続分2000万円から生前贈与額1000万円を差し引く=Aの相続分は1000万円
特別受益になるもの
被相続人から利益を受けたらすべて特別受益になるわけではありません。どのような利益が特別受益になるのかは、民法で決められています。
具体的には、以下のものが特別受益となります。
- 婚姻・養子縁組のための生前贈与
- 生計の資本としての生前贈与
- 遺贈
以下では、代表的なケースを紹介します。
婚姻・養子縁組のための生前贈与
婚姻・養子縁組のための生前贈与としては、以下のようなものがあります。
- 結婚資金の援助(結納金や新居の購入資金)
- 養子縁組に伴う持参金
生計の資本としての生前贈与
生計の資本としての生前贈与には、さまざまなものがあります。具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅購入のための資金援助
- 住宅のための不動産の贈与
- 事業資金としての贈与
- 借金の肩代わり
- 高額な留学費用
- 医学部や私立大学への入学金・学費
遺贈
遺贈とは、遺言によって相続人または第三者に相続財産を贈与することです。この遺贈によって相続人に相続財産を贈与した場合も、特別受益の対象になります。
特別受益に当たらないケース
前記のとおり、すべての利益や援助が特別受益に含まれるわけではありません。例えば、以下のようなものは特別受益にはならないことが多いです
- 生活費や日常的な仕送り:家族・親族間での扶養義務の範囲内のものとして、特別受益には当たらないと判断されることが多い
- 進学のための一般的な学費:小学校・中学校・高校などの進学費用は特別受益に当たらないと判断されることが多い。また、他の相続人(特に兄弟姉妹)と同程度であれば特別受益とは扱われにくい
- お祝い金や慣習的な贈り物:結婚祝い金や成人祝いなど、社会通念上特別と言えない程度の金額であると、特別受益に当たらないと判断されることが多い
学費援助金の場合
上記のとおり、学費援助金は、一般的な学費の援助は特別受益に当たらないと判断されるのが通常です。特に、小学校・中学校・高校の学費は、よほど特別の事情がない限り、特別受益に当たると判断されることは少ないでしょう。
一般的な大学の進学費用や授業料も、他の相続人と比べて特別高額であるような場合を除いて、特別受益とは判断されにくいでしょう。
逆に、医学部の入学金・授業料など他と比べて特に高い学費が必要となる場合や高額の留学費用などは、特別受益と判断される可能性があります。
遺産分割において特別受益を主張する場合の注意点
他の相続人が特別受益を受けていた場合、相続分の調整を行うためには、遺産分割において特別受益があったことを主張しなければいけません。
以下では、遺産分割において他の相続人に特別受益があることを主張する場合の注意点について説明します。
特別受益に当たるのかを確認する
前記のとおり、どのような利益・援助でも特別受益に該当するわけではありません。
特に、生計の資本としての生前贈与の場合には、ある程度、特別と言えるような贈与でなければ、特別受益には当たらないと判断されることがあります。
具体的には、以下の点に注意しておく必要があります。
- 親族間の扶養義務の範囲内か否か:扶養義務の範囲内の贈与・援助は、特別受益には当たらないと判断されるのが通常です。
- 他の相続人と比較して特別な利益か否か:仮に生前贈与があっても、他の相続人も同じような贈与・援助を受けている場合には、特別受益に当たらないと判断されることがあります。
特別受益があったことの証拠を用意する
遺産分割において、他の相続人に「特別受益があった」と主張する場合、証拠なしにただ主張だけをしても、他の相続人からの理解を得られませんし、遺産分割調停や審判において裁判所に認めてもらうこともできません。
特別受益があったことを裏付ける証拠を揃えておく必要があります。
遺贈の場合は、遺言書に記載があるので、その遺言書があれば特別な証拠はあまり必要とならないでしょう。しかし、生前贈与の場合には、何らかの証拠を見つけておかなければいけません。
例えば、以下のような証拠が必要となるでしょう。
- 贈与契約書
- 被相続人の預金通帳、振込記録、領収書:被相続人から特定の相続人に対して金銭の交付があったことを示す証拠
- 登記事項証明書、自動車登録事項証明書など:贈与されたものが不動産や自動車などである場合の証拠
- 被相続人のメモ:特定の相続人に贈与をしたことを記載したメモなども証拠になることはあります
持ち戻し免除の意思表示がないかを確認する
被相続人は、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」をすることができます。特定の贈与などについては、持ち戻しをしないようにしておけるのです(民法903条3項)。
持ち戻し免除の意思表示が遺言書などで残されている場合、指定された贈与などについては持ち戻し計算できません。
遺産分割において特別受益を主張する場合には、この持ち戻し免除の意思表示がないかどうかを確認しておく必要があります。
まとめ
不公平な生前贈与などがあった場合、特別受益を主張する必要があります。
しかし、特別受益を認めてもらうのは、簡単ではありません。遺産分割において特別受益を主張・立証するためには、法的な知識が必要となるからです。
適切に特別受益の主張・立証を行いたいとお考えの場合は、早めに弁護士へ相談し、しっかりと準備を進めておくことが大切です。