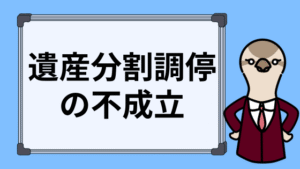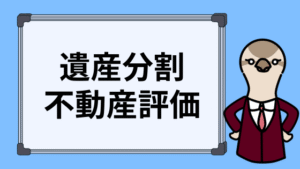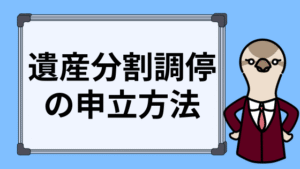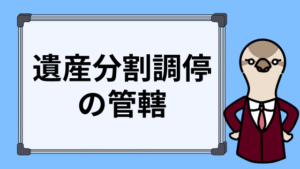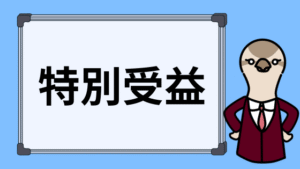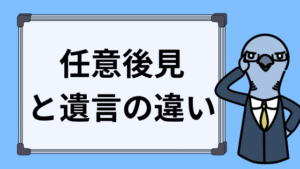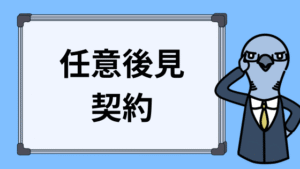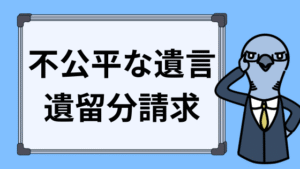認知症だった親が書いた遺言書は無効?「遺言能力」が争点となる場合の立証方法
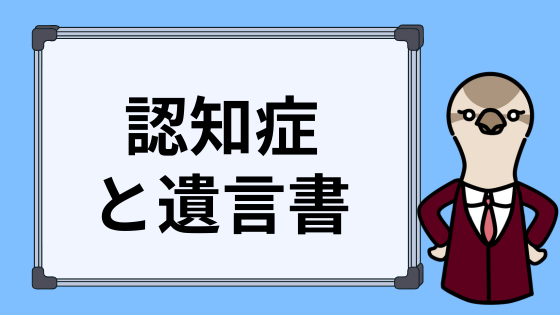
遺言書が残されている場合、それが正しい方式で作成された有効なものであれば、その遺言書に沿って、遺産の分配が行われます。
もっとも、その遺言書を作成したのが認知症だった親であるという場合には、遺言を作成した人の「遺言能力」が問題となってきます。
本記事では、認知症だった親が書いた遺言書など「遺言能力」が問題となるケースやその場合の立証方法について解説します。
認知症の親が書いた遺言書が無効となるのかどうかなどでお困りの方がいらっしゃいましたら、ご一読ください。
認知症の親が書いた遺言書は無効になるのか?
認知症の人が作成した遺言書だからと言って、必ず無効になってしまうわけではありません。
遺言が有効となるための要件として「認知症でないこと」が求められているわけではないからです。
しかし、遺言が有効であるためには、遺言書を作成した人(遺言者)に「遺言能力」があることは必要であるとされています。
したがって、遺言者に遺言能力がなかった場合には、その遺言書は無効になります。
逆に、遺言者が認知症であったとしても、遺言能力が備わっていたと言えるのであれば、遺言書は無効にはなりません。
遺言能力とは?
法律関係を発生させる意思に基づいて行う自分の行為によって発生する結果を理解して判断できる能力を意思能力と言います。意思能力を欠く法律行為は、無効となります。
この意思能力を遺言の作成の場面に当てはめたものが、遺言能力です。
すなわち、遺言能力とは、遺言の内容や遺言に基づいて発生する法律効果を理解できる能力のことです。
ある裁判例では、遺言能力を「遺言の内容を理解し、その法律効果を弁識することができる能力」と定義し、その有無の判断に関して「遺言者の精神上の障害の有無、内容及び程度を基礎としつつ、遺言の内容や遺言をするに至った経緯等を総合的に考慮すべきである。」と述べたものがあります(東京地方裁判所令和5年12月22日)。
この遺言能力を欠く人が作成した遺言書は、無効となります。
第九百六十三条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
認知症と遺言能力
認知症の場合、認知機能の低下によって、通常よりも判断能力や理解能力が減衰しています。
そのため、遺言を作成した人が認知症であった場合、遺言の内容や遺言に基づいて発生する法律効果を理解せずに作成してしまっている可能性があります。
つまり、遺言能力がないのに遺言書を作成してしまった可能性があるということです。
もし遺言能力がないのに遺言書を作成していたのであれば、その遺言書は無効です。
したがって、認知症の人が作成した遺言書が無効となるのかどうかは、その人に遺言能力があったと言えるのかどうかが争点となります。
遺言書の無効を主張する手続
認知症の人が作成した遺言書が無効であることは、遺言によって利益を受ける相続人などに対して主張することになります。
遺産相続の問題ですから、話し合いが望ましいことは確かです。遺言がある場合でも、相続人や利害関係人全員の話し合いによって、遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。
しかし、話し合いが難しいまたは話し合いができない場合には、裁判手続を利用して、遺言書の無効を争うことになるでしょう。
遺言書の無効を争う裁判手続としては、原則として、まず、家庭裁判所において遺言無効確認調停を行う必要があります。
調停では、家庭裁判所の裁判官または調停委員が間に入って、話し合いをすることになります。
調停でも話がつかなかった場合には、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺言能力が争点となる場合の立証方法
認知症だからと言って、常に遺言能力がないとは言えません。認知症にも症状や程度の違いがあるからです。
そのため、遺言者が遺言書を作成したときに認知症であったというだけでは、遺言能力がないとまでは言えません。
また、認知症の症状や程度も一律ではありませんから、それぞれの個別具体的なケースごとに、遺言能力があったのか否かを判断するほかありません。
以下、遺言能力が争点となる場合の立証方法のポイントについて説明します。
認知症の症状や程度
認知症の人の遺言能力について考慮される第一のポイントは、言うまでもなく、認知症の症状や程度です。
症状や程度が重度のものであれば、遺言能力を否定する方向に働きます。他方、軽度にすぎないのであれば、遺言能力を肯定する方向に働きます。
認知症の症状や程度を立証するために最も重要な証拠は、遺言者の医師の診断書・カルテ・医療記録などです。
認知症診断においては、長谷川式簡易知能評価スケールやミニメンタルステート検査などの神経心理学検査が行われます。これらの検査結果も証拠となります。
また、遺言者が介護サービスなどを受けていた場合には、遺言者の状態などを記録した介護記録や看護記録があります。これらも重要な証拠として利用できます。
遺言者の主治医や介護事業者などに対して開示を求めて、これらの医療記録などを収集しておく必要があります。
場合によっては、主治医等に認知症の症状に関する鑑定書を作成してもらったり、証人になってもらったりすることもあります。
遺言作成時の状況
自筆証書遺言の場合ですと、遺言者が誰もいないところで作成していることが多いため、遺言作成時の状況が分からないことが多いかもしれません。
しかし、公正証書遺言の場合であれば、公証人や証人が遺言書作成に関与しています。場合によっては、医師が立ち会っていることもあります。
これらの人の証言は、遺言作成時の状況を立証するための証拠になります。
遺言作成時における遺言者の体調や精神状態などが優れていなかった場合には、遺言能力を否定する方向に働き、逆に良好であった場合には、遺言能力を肯定する方向に働きます。
遺言作成前後の状況
遺言作成時の状況が分からない場合には、遺言作成前後の状況を立証して、そこから遺言作成時にどのような状況であったのかを推測するという方法をとることになります。
前記の医療記録や同居の家族の証言などを証拠として、遺言作成前後の状況を立証することになるでしょう。
遺言書の内容
遺言書それ自体の内容も、遺言能力の有無を判断するための証拠になります。
遺言の内容が複雑な場合、認知症の遺言者が、複雑な遺言の内容や遺言に基づいて発生する法律効果を理解して作成したものとは考えにくいところがあります。
逆に、遺言の内容が簡単なものである場合、認知症の遺言者であっても、十分にその内容等を理解して作成したと考えることができます。
そのため、遺言内容が複雑であることは、遺言能力を否定する方向に働き、遺言内容が簡単であることは、遺言能力を肯定する方向に働きます。
また、遺言者の生前の言動と遺言書の内容が一致していないような場合も、遺言者が自分の意思ではなく、誰かに誘導されて遺言書を作成したことをうかがわせる事情になることもあります。
遺言書の筆跡・状態
遺言書の内容だけでなく、遺言書の筆跡や遺言書の状態なども、遺言能力を判断するための証拠になります。
遺言書の筆跡があまりに乱れている場合や加除訂正が著しく多いような場合には、遺言能力がない状態で作成されていたと判断される方向に働くことがあります。
遺言書が無効かどうかの判断方法
遺言能力を欠くものとして遺言書が無効となるかどうかは、これまで述べてきたようなさまざまな事情を総合的に考慮して判断されることになります。
したがって、遺言書の無効が認められるためには、いずれかだけ立証すればよいわけではありません。多くの事実を立証して積み重ねなければならないのです。
まとめ
以上のとおり、認知症の親が書いた遺言書だからと言って、必ずしも遺言書が無効となるわけではありません。認知症であっても、遺言能力があるならば、その遺言書は有効です。
遺言書の無効を争う場合には、単に認知症であるというだけでは足りず、遺言能力がないことを立証する必要があります。
実際のところ、遺言の無効を立証するのは、容易ではありません。かなり専門的な知識や判断が必要です。
したがって、もし遺言書の無効を争うというのであれば、やはり弁護士に相談すべきでしょう。