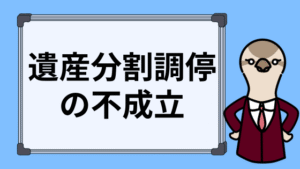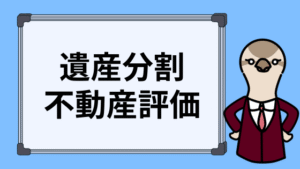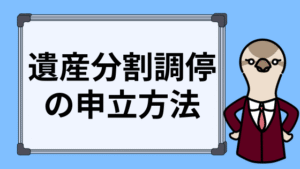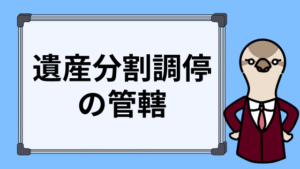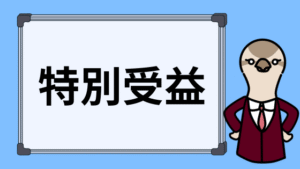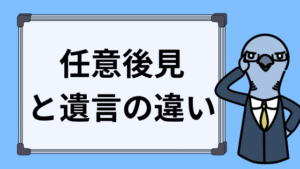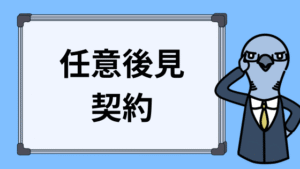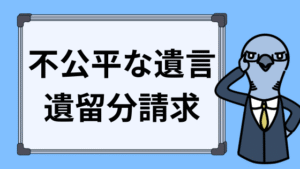【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い
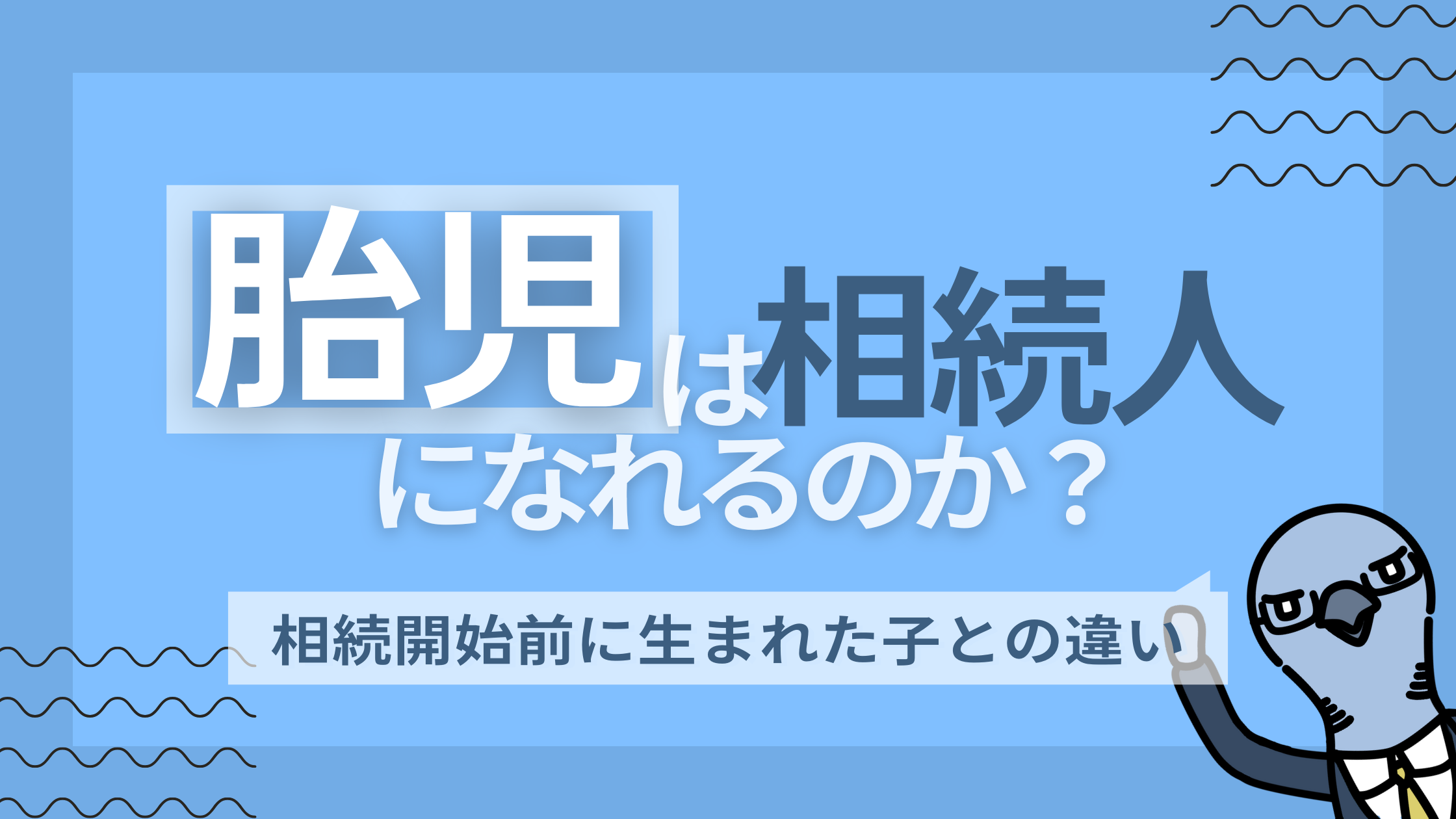
相続が開始されると、亡くなった人の遺産は、相続人に受け継がれます。この相続人には、亡くなった人の子も含まれます。
もっとも、母親の胎内にいる胎児はどうなるのでしょうか?まだ生まれていないとはいえ、胎児も子であることに変わりありません。
本記事では以下について解説していきます。
・胎児も相続人になれるのか?
・相続人になれるとしてすでに生まれている子と相続において違いがあるのか?
■相続人調査に関するコラム・解決事例一覧■
・【弁護士解説】誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位のキホン~
・【弁護士解説】異母兄弟が死亡した場合の相続権/割合/放棄/遺言書のポイント
・配偶者は常に相続人?婚姻関係がある場合と内縁関係の違い
・【弁護士解説】胎児は相続人になれるのか?相続開始前に生まれた子との違い
・【弁護士解説】相続欠格と廃除|相続人になれないケースとは
胎児の権利・義務
胎児も相続人になれるのかを説明する前に、そもそも胎児に法律上の権利や義務が認められるのかについて考える必要があります。
法律上の「人」
法律で定められた権利を享受したり、義務を課されたりするのは、「人」です。法的な言い方をすると、権利義務の主体または客体になるのは「人」です。
この「人」の始期は、「出生」の時です。つまり、生まれた時に「人」として、権利義務の主体または客体になるのです
人の「出生」の時期
人の「出生」の時期については、以下の2つの考え方があります。
- 全部露出説:母親の身体から胎児の身体が全部出てきた場合が「出生」に当たるとする考え方。
- 一部露出説:母親の身体から胎児の身体の一部でも出てくれば「出生」に当たるとする考え方。
民法では、全部露出説が通説とされています。
したがって、母親の身体から胎児の身体が全部出てきてはじめて「人」と認められるということになります。
身体の一部だけしか出ていない場合は、まだ「人」とは言えません。
胎児に法律上の権利・義務は認められるのか?
前記のとおり、母親の身体から胎児の身体が全部露出されてはじめて「人」となり、法律上の権利や義務が認められることになります。
したがって、まだ母親の胎内にいる胎児は、法律上の「人」とは言えず、法律上の権利や義務は認められないのが原則です。
胎児は相続人になれるのか?
前記のとおり、胎児には法律上の権利義務が認められません。そのため、相続人にもなれないように思えます。
しかし、胎児には、相続について特別の規定が設けられています。これにより。
胎児も相続人になることがあります。
以下、詳しく説明します。
胎児の出生擬制
胎児とは言っても、すでに生命としては誕生しています。
例えば…
被相続人(遺産を遺す側の人)が亡くなる直前に生まれていれば相続人になり、亡くなった直後に生まれていれば相続人にならないというのは、妥当ではありません。
そこで、民法では、例外的に、「胎児は、相続については。既に生まれたものとみなす」と規定されています(民法886条1項)。
つまり、相続については、胎児であっても、「人」として扱うということです。これを、胎児の出生擬制と言います。
したがって、胎児も、相続人になることがあるのです。
胎児が相続人になる場合
被相続人が亡くなると、その死亡時に相続が開始され、被相続人の遺産(相続財産)は、相続人に受け継がれます。
誰が相続人となるかは、民法で決められています。そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
相続人となるのは、被相続人の「子」、「直系尊属(直系の先祖に当たる人。父母や祖父母など。)」、「兄弟姉妹」および「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。
生まれてくる胎児が、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」であった場合、相続人になることがあります。
胎児の相続権行使
胎児が相続人になる場合、どのようにその相続権を行使するのかについては、出生擬制をどのように捉えるかによって、以下のような考え方の違いがあります。
- 解除条件説(制限人格説):胎児の時点で相続が開始された場合、胎児はその時点で相続権を行使できるものの、死産であった場合には、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったことになるとする考え方です。
- 停止条件説(人格遡及説):胎児の時点で相続が開始されたとしても、その時点では相続権を行使できず、出生した場合に、相続開始時にさかのぼって相続人であったことになり、相続権を行使できるとする考え方です。
遺産相続の実務では、停止条件説が採用されています。
したがって、胎児が出生した場合に、相続権を行使できることになります。
もちろん、生まれたばかりですから、自分で相続権を行使できるはずはありません。実際には、生まれた子の法定代理人(父母)が、その子に代わって相続権を行使することになります。
ただし、生まれた子の法定代理人も相続人である場合は、その子と法定代理人との間で利益相反になってしまいます。
そのため、この場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらって、その特別代理人が、生まれた子に代わって相続権を行使することになります。
胎児と相続開始前に生まれた子との違いはあるのか?
相続開始時に胎児であった子が、被相続人の「子」として相続人になる場合、相続開始前に生まれた子と比べて、相続において違いがあるのでしょうか?
結論から言うと、相続開始時に胎児であった子と相続開始前に生まれた子に違いはありません。
どちらも、「子」として同じ扱いです。相続開始の時に胎児であったからと言って、相続開始前に生まれていた子よりも相続分が少ないなどということはありません。
「子」の相続分に違いはありません
被相続人の「子」は、第1順位の相続人です。
第1順位とは、他に被相続人の直系尊属(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)がいたとしても、子が相続人になるということです。
子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。ただし、配偶者がいる場合には、子と配偶者が相続人になります。
子が複数人いる場合には、その子の人数で頭割りをして相続分が決まります。例えば、子が3人いれば、それぞれ3分の1ずつ相続するということです。
なお、配偶者がいる場合は、子が2分の1、配偶者が2分の1となります。子が複数人いる場合は、子の2分の1の相続分を子の人数で頭割りすることになります。
例えば…
子が3人と配偶者が相続人の場合は、配偶者は2分の1となり、子は、残りの2分の1を3人で割ることになるので、それぞれ6分の1ずつとなります。
これら「子」の相続分は、相続開始時に胎児であった子と相続開始前に生まれた子で、違いはありません。
相続人としての権利も違いはありません
相続分以外の相続人としての権利についても、相続開始時に胎児であった子と相続開始前に生まれた子で違いはありません。
例えば…
相続開始時に胎児であった子も、遺産分割にも参加できます。胎児が生まれてくる前に、胎児を除いた遺産分割が成立してしまっていた場合には、やり直しになります。
そのため、胎児がいる場合には、胎児が生まれてくるのを待って遺産分割をするのが通常です。
また、相続開始時に胎児であった子も、生きて生まれてくれば、相続放棄をすることも可能です。ただし、出生から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要はあります。
相続税の申告期限には違いがあります
相続人としての権利などについて、相続開始時に胎児であった子と相続開始前に生まれた子で違いはありませんが、相続税の申告期限には違いがあります。
相続税の申告期限は、相続開始から知った日の翌日から10か月以内とされています。相続開始前に生まれた子の場合には、この期間内に税務申告をすることになります。
他方、胎児の場合、この期間内に胎児が出生しなかったときには、他の相続人は、胎児はいないものとして相続税を申告しなければなりません。
胎児はいないものとして相続税を申告した後に胎児が出生した場合は、胎児の法定代理人が、胎児の出生を知った日の翌日から10か月以内に、胎児の相続税を申告し、他の相続人は更生の申告をすることになります。
まとめ
以上のとおり、相続が開始した時に胎児であっても、生きて生まれてくれば、「子」または「兄弟姉妹」として相続人になります。
胎児が「子」として相続人になる場合、相続開始前に生まれた子と同じ扱いがされます。胎児だからと言って、相続開始前に生まれた子よりも相続分が少ないなどということはありません。
ただし、胎児であるため、通常の場合と異なる手続や考慮も必要となります。胎児の相続についてお困りの場合は、弁護士に相談することをお勧めします。